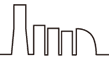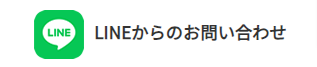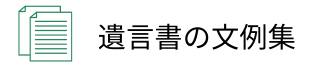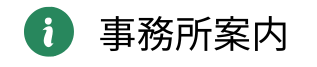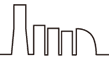LGBTという言葉がだいぶ浸透してきた近年ですが、現在、日本では同性婚が認められていません。
つまり、同性カップルはどんなに長く一緒にいても法律上は他人扱いになってしまいます。これはすなわち、相続の場面において、同性パートナーに法律上の保障はないということを指します。
もっとも同性婚の是非をめぐる議論は続いており、2021年3月に札幌地方裁判所で、婚姻の法的効果が同性カップルに及ばないのは平等権を認めた憲法第14条1項に反するという判例が出たりもしています。
ですが、まだ法律はLGBTに即したものになっているわけではありません。
遺産相続は法律に則って進められますので、事前に対策を講じておかないと同性のパートナーは他人扱いとなり、何も相続が受けられなくなってしまうので、気をつけなくてはいけないのです。
このような実情の中、同性パートナーが結婚せずに将来へ備える対策として、公正証書を活用する方法が挙げられます。
今回の記事は、同性パートナーが公正証書を活用する方法について、分かりやすくお伝えするために「座談会風」にお伝えしていきます。
この記事が同性カップルの将来に悩んでいる方の助けになれば幸いです。
目次
同性パートナーの将来に起こるリスク
まずは前提情報として、何も対策をしない場合に同性パートナーの将来に起こるリスクについて見ていきましょう。
今回は、同性カップルのAさんBさんカップル、CさんDさんカップルにお越しいただき、将来について備えておくべきことについて話し合ってみましょう。
A「よろしくお願いします」
B「早速ですけど、将来の懸念点と言えば、やはり相続になってくるかなと思っているんです」
同性パートナーの将来に起こるリスクとしては、次のような例が挙げられますね。
- 同性パートナーは法定相続人になれない
- パートナー側の親族と遺産相続をめぐって争う
- パートナー名義の家を相続した相続人から、家を追い出されてしまう
- 共同で経営していた事業から締め出されてしまう
- パートナー名義の預金を引き出せなくなり、日々の生活にも困窮してしまう
- パートナーが事件・事故で亡くなっても公的な遺族補償が認められない
C「そうだね。同性パートナーは法定相続人になれないしね」
D「遺言がないと遺産分割協議になるんだけど、これには参加できるのかな?」
C「残念ながら、同性のパートナーはこの法定相続や遺産分割協議に参加することができないんだよね」
D「なんだかやるせないね…」
B「うん、こういうの絶対避けたい」
同性パートナーの将来に役立つ公正証書
A「こないだ、行政書士さんに聞いたんだけど、同性パートナーは、公正証書を活用すると色々と対策できるんだって。とるべき4つの対策ってのがあるんだって}
公正証書とは、公証人(法務大臣が任命する公務員)が作成する公文書のことです。公正証書の原本は公証役場で保管され、紛失・改ざんの恐れもなく、さらに公証人が当事者の意思を確認して作成するため、信頼性が高いとされています。
そして、同性パートナーの将来に役立つ公正証書としては、次のような例が挙げられます。
- 公正証書遺言
- 任意後見契約書
公正証書遺言
公正証書遺言とは、その名のとおり公正証書による遺言です。自分で作成する「自筆証書遺言」と異なり、作成するために費用が発生しますが、社会的な信用が高く、公証人という専門家が作成してくれるので無効になる心配が少ないことがメリットです。
同性のパートナーがいることを親族にカミングアウトできていない場合や、親族からの反発が予想されるような場合、自筆証書遺言だとあらぬ疑いや無効の訴えを起こされてしまう可能性もあります。
しかし公正証書遺言があれば、同性のパートナーにも遺産が「比較的」スムーズに渡すことができます。
ただし、法定相続人が最低限の相続財産を請求できる権利(遺留分)の請求(遺留分侵害請求)を起こされた場合、同性パートナーは法定相続人に対して金銭で請求額を支払う必要があります。
遺言書を作成の際はこの遺留分に配慮した内容にすることもトラブルを抑える点においては有用です。
合わせて読みたい:遺留分とは?具体例や侵害された遺留分請求方法を分かりやすく解説!
また、遺言内容を実現する人を決めておかないと、相続人にとって遺言の内容が不利だと感じられる場合、遺言内容をスムーズに実現できない可能性があります。確実に遺言内容を執行してもらうため、遺言を執行するための権利と義務が集約された遺言執行者を、遺言の中で指名しておくこともおすすめです。
合わせて読みたい:遺言執行者とは?実行する内容・権限の書き方を行政書士が分かりやすく解説
さらに、同性のパートナーは法律上の相続人ではないので、遺言によって相続人以外の人に財産を譲る「遺贈」という形になります。
財産を具体的に指定して譲る「特定遺贈」と、割合のみを指定して譲る「包括遺贈」があるが、包括遺贈にすると借金などのマイナスの財産も引き継がれてしまうことには注意しなければなりません。
合わせて読みたい:包括遺贈とは?特定遺贈との違いと包括受遺者の権利義務について行政書士が解説!
このように、同性パートナーへ財産を残すための遺言書を作成する際は、注意すべきことが多々あります。横浜市の長岡行政書士事務所は、これまでも同性カップルからの相談を受けており、実務的なアドバイスも可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。公正証書遺言の作成を徹底的にサポートいたします。
合わせて読みたい:LGBTや同性カップルの遺言書の作り方とは?相互遺言について行政書士が解説
任意後見契約書
B「公正証書遺言が必要なのは分かったけど、これは死後に備えるためのものだよね?生前の生活に役立つ公正証書もあるのかな?たとたばパートナーが認知症になったりしたら、法律上の夫婦なら色々と手続できそうだけど、同性カップルはどうすればいいんだろう」
A「そんなときは、任意後見制度だね。この制度は皆知っているかな?」
D「確か、認知症などの障害のある方にサポートする人をつけて、判断能力を補って、社会参加を継続してもらうための仕組みだったかな?」
A「正解!サポートをする人の事を後見人として、介護や世話をするのではなく財産管理や契約の代理、つまり頭の代行をするわけだね」
B「身体の代行をしてもらうのは、介護士さんたちだもんね」
A「成年後見制度には2種類あるんだけど、できれば同性カップルは、任意後見契約を結んでおいた方がいいね」
法定後見=本人の判断能力が衰えたあとに、家庭裁判所に申し立てをし後見人をつけてもらう。後見人は家庭裁判所が選定し、代理の内容は法律で決まっている。
※その他に本人の判断能力の状況により保佐、補助という制度もあり、これらをまとめて成年後見制度といわれる。
任意後見=自分の判断能力が衰えたときに備えて、自分で後見人候補を見つけて契約し、その代理権の内容や報酬等も当事者間で決定しておく。
合わせて読みたい:委任契約、任意後見制度と遺言執行者とは?生前から死亡後まで安心の制度について解説!
C「任意後見契約を結ばないまま、例えばパートナーが認知症になっちゃうと、もう一方のパートナーは相手の契約を代行したり財産管理をすることができないってわけか」
D「だね。パートナーの入院の手配やパートナー名義の預金の引き出しができなくなる」
A「そうなんだよ。さすがにそれは不便だということで、家庭裁判所に法定後見を申し立てることはできるんだけど…」
B「…法定後見人は事情を知らない他人が指名される可能性があるよね。その人に、同性パートナーへの理解が得られるかどうかもわからないし」
A「でもパートナーを任意後見人に指名しておけば、色々と代理してもらえるから安心だよね」
C「元気なうちに任意後見契約、覚えておくよ」
A「しかも、任意後見は登記されるから、登記証明書を公的なパートナー証明として使えるんだよ。その証明書を提出することで銀行のペアローンが利用できるようになったり病院での立ち合いが認められたりと、2人の関係を証明するために使うことができるってわけ。そして任意後見契約は、公正証書で作らないといけないんだ。」
横浜市の長岡行政書士事務所は、任意後見契約書の作成もサポートしています。
同性パートナーが公正証書を活用するなら行政書士へ相談!
ここまで紹介したとおり、同性パートナーは法律上は夫婦として認められないものの、公正証書を結んでおくことで法的な保護を受けることも可能です。
とくに公正証書遺言と任意後見契約書をセットで作成しておくことで、同性カップルの将来によりきめ細かに備えることができます。
横浜市の長岡行政書士事務所ではこれまでも何度か同性カップルからご相談をいただいており、公正証書遺言・任意後見契約書のどちらも作成をサポートできます。もし詳しい話しを聞きたいという方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料で対応しています。