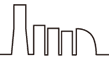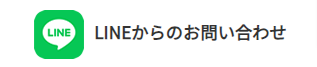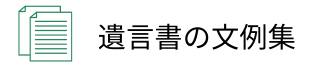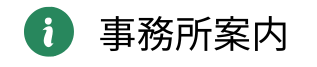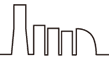「遺産分割協議が紛糾しそうで心配です。遺産分割で揉めないためにできる事前準備はありますか?」というお悩みはよく聞きます。
相続が「争族」となってしまった、という話をちらほらと聞くようになりました。
そもそもこの争族という言葉が作られたこと自体が、社会に一定数の相続争いが起きていることの証明だとも言えます。
そこでこのコラムでは、横浜市で相続手続をサポートしている立場から、相続争い(遺産分割協議がまとまらない場合)の典型的なケースを6パターン紹介し、その原因や対策を解説していきたいと思います。遺産分割で揉めないための事前準備について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
遺産分割協議が揉める例
遺産分割協議で揉めてしまう例としては、次の6つが挙げられます。
- 自身の寄与分を主張して納得しない相続人がいる
- 既に特別受益を受けている相続人がいる
- 被相続人が再婚をしている
- 相続人の中で音信不通(行方不明)の人がいる
- 相続財産の中に不動産がある
- 遺産分割が終わる前に次の相続が始まってしまった
それぞれどのような状況なのか、詳しく見ていきましょう。
自身の寄与分を主張して納得しない相続人がいる
寄与分とは故人(=被相続人)がまだ生きていた時に特別の貢献をした相続人に対し、貢献の度合いに応じた相続分をプラスすることができる制度のことをいいます。
より詳しい説明を下記別コラムで行っていますので、参照してみてください。
あわせて読みたい>>>親の介護を頑張った!相続の時には寄与分として考慮されるの?
揉めてしまう例としては、被相続人が生前に介護状態にあり子のうちのひとりが介護を一手に担っていたような場合です。
親の介護を行っていた子は多めの遺産を「寄与分」として主張するかもしれませんが、他の子は平等な分配を主張するかもしれません。また、その寄与分の度合いをどう計算すべきかが争点になる可能性があります。
これまでの判例によれば、寄与分と認められる可能性が高い要件は下記4点になります。
- 長期間の献身があったか
- 専念しなければならなかったか
- 被相続人との関係性から期待される以上の程度を越えた献身があったか
- その献身に対して対価が支払われていないかどうか
しかしながら、法に判断をゆだねると寄与分を主張する相続人の感情との間にずれが生じる場合が多く、寄与分が認めてもらうのが難しい傾向にあります。
相続人同士が遺産分割協議で話し合う場合は、寄与分を主張する相続人はなるべく自身の献身の記録(日記、かかった費用のレシート等)などを準備しておくと他の相続人に納得してもらうことができて遺産分割がまとまる可能性も高くなります。
なお、寄与分と似ていますが、別の「特別寄与料」という制度もあります。
決定的な違いは寄与分が相続人のみに認められるのに対して、特別寄与料は「相続人以外の親族」に認められるという違いがあります。
具体的な例としては長年介護をしてくれた息子の妻などが挙げられます。
子の配偶者は法て定められた相続人(=法定相続人)にはなれないので本来であれば相続する権利はありませんが、献身の度合いによって遺産を分けることで報いてあげようとする趣旨です。
特別寄与料に関してもなるべく客観的な資料を揃えておくと、遺産分割協議で他の相続人から認めてもらえる可能性が高くなります。
あわせて読みたい>>>子の配偶者に不動産を相続させる方法とは?遺言書活用法を行政書士が解説!
既に特別受益を受けている相続人がいる
特別受益とは、相続人の中に既に被相続人から利益を受け取っている場合のその利益の事を指します。
例えば子が二人いて長男が海外留学費用として生前の父から1,000万円を既に受け取っていた場合、父が亡くなった後3,000万円の遺産を長男と次男で1,500万円ずつ等しく分けたのでは次男は不公平だと感じこのような遺産分割案には同意しない可能性があります。
この場合の一つの解決策として、遺産を長男に500万、次男に2,500万円に分けることで帳尻を合わせることができます。
あわせて読みたい>>>特別受益とは?生前に親から多額の援助を受けた場合は相続に影響するため注意
しかしながら、長男も事情がありより多くの遺産が欲しい場合自分の権利を主張しすんなりとこの特別受益を認めないかもしれません。また、仮に次男も大学の学費を父に出してもらっているような場合は今度は長男が不公平だと感じるかもしれません。
このように、どこまで特別受益を遺産の一部とするかがポイントとなってきます。
個別のケースによって事情が異なるので一概に線引きするのは難しいのですが、判例により特別受益とされたケースは以下の通りです。
- 結納金、結婚持参金を既に受け取っていた
- 家の購入資金援助を受けていた
- 事業を始めるための開業資金を援助してもらった
- 借金を肩代わりしてもらった
- 扶養の範囲を超える生活費を援助してもらった
次に、判例により特別受益とされなかったケースを紹介します。
- 扶養の範囲内で生活費の援助をしてもらった
- 結婚式費用を出してもらった
- 生命保険の死亡保険金を受け取っていた
特別受益と認められなかったケースについて、判例を一つ具体的に見てみましょう。
京都地方裁判所平成10年9月11日の判例では、親が開業医で長男のみが医学部に進学し、学費及びその他の援助を他の兄弟より多く受けていたことが特別受益として認められるかどうかが争われました。
裁判所は以下のような事情から、特別受益に該当しないと判断しました。
- 親が開業医であり十分な資産があった
- 親は長男による家業承継を希望していて、長男本人や他の兄弟もその家業承継に同意していた
- 他の兄弟も大学教育を受けていた
この事例では、長男は多くの学費援助を受けていたものの家業の事情や他の兄弟とのバランスも崩れていなかったために、特別受益性が否定されました。
しかしながら、もし家業が開業医でなく一般家庭であったり、他の兄弟が大学に行ってなかったりと差があった場合は特別受益性が認められた可能性があります。
対策としては実際に相続が始まる前にまずは自分を含めた相続人がどれだけ金銭を受け取っていたかをなるべく把握して、専門家に相談しアドバイスを求めることをお勧めします。
遺産分割協議が始まってしまった後に、お互いにもらった金額を指摘しあうのは感情のもつれを生じさせてしまうことになりかねません。できるだけ事実に基づいた遺産分割協議にするためにも、事前準備をしておくようにしましょう。
被相続人が再婚をしている
離婚届けを提出することで、配偶者との法律上の夫婦関係が消滅し他人に戻ります。
しかし二人の間に子がいる場合、どちらに引き取られたとしても親子関係は消滅しません。
仮に先妻との間で子がいて再婚し新たに子が生まれた場合、先妻の子と後妻の子はどちらにも等しく相続権が発生します。子の相続権には優劣はないので、後妻の子と先妻の子は同じ額の相続を受けることができます。
問題が発生しやすいのは以下の場合です。
- 前妻の子が音信不通になっていて、相続人が全員参加しないといけない遺産分割協議をおこなうことができない。
- 前妻と後妻の家族との折り合いが悪く、前妻の子が相続放棄を迫られた。
- 遺言書はあるが前妻の子への相続の配慮がなく、前妻の子から急に遺留分侵害請求を受けてしまった。
また、後妻に連れ子がいる場合は養子縁組をしないと法律上の親子関係は成立せず、相続を受けさせてあげることができません。
あわせて読みたい>>>連れ子に遺産を譲りたい時に気をつけるべきポイントと解決策を行政書士が解説!
このように再婚の場合は法律上の関係が複雑になるだけでなく、遺産分割会議で前妻と後妻が顔をあわせるはめになったりと思わぬトラブルに発展する可能性があります。
相続人の中で音信不通(行方不明)の人がいる
相続手続きの中でまず最初にやらなければならないのは、相続人を確定させることです。
誰が相続人かなんてもうわかってる・・・と思うかもしれませんが、意外なところから相続人が出てくることも多くそうなると相続がやり直しになってしまいます。
そのような事態を防ぐため、被相続人の戸籍を生まれたときから全て集めて配偶者・子供・両親などを漏れなく確認し、相続人をしっかりと確定させることが重要です。
ところで、せっかく相続人が確定できてもその相続人の一人と連絡がとれない場合はどうなるのでしょうか。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必須なので、相続手続が止まってしまうことになります。
対策としては、生前に推定相続人全員の連絡先を確認しておくことや、興信所に依頼して相続人を探してもらうことが挙げられます。
また、家庭裁判所に申し立てて失踪宣言を出してもらう事もできますが、手間と時間がかかってしまい相続手続が大幅に遅れてしまうおそれがあります。
やはりこのような相続人が見つからないことによる相続の停止を避けるには、遺産分割協議をしなくて済むために遺言を遺しておくことが一番だと言えます。
合わせて読みたい:不在者財産管理人とは|相続人が失踪し見つからない時はどうする?
相続財産の中に不動産がある
土地・建物といった不動産は分割ができないので、遺産を相続人の間でどう分割するかが問題になりやすいです。
特に遺産の大部分が不動産だった場合は、どう分けるかの選択肢が限られてしまいます。
例として、親1人子2人の家族で親が亡くなった時の遺産が実家の土地建物だけであった場合を考えてみましょう。
土地を長男、建物を次男と相続させると、相続の後売却するときに問題となります。
別の人が所有している土地の上に立っている建物の買い手を探すのは難しいからです。
土地と建物を長男と次男の共同所有にする「共有分割」という方法もありますが、これも後々の売却や建て替えで共有者全員の合意が必要なため揉める可能性が大です。
対策としては、下記の2つが挙げられます。
・代償分割…不動産を相続した相続人が他の相続人に対価を支払う
・換価分割…不動産を現金化し現金を相続人間で均等に分ける
代償分割の場合は対価として現金を払う必要があり、不動産を相続した相続人が現金の準備ができない場合は負担となってしまう可能性があります。
換価分割は最も公平に遺産を分割できるので満足度が高い方法ですが、売却までに時間がかかったり、思い出深い実家を売るという心理的抵抗を感じたりという難しさもあります。
あわせて読みたい>>>遺言により不動産を売却して相続人間で分配する流れと税金関係を解説
遺産分割が終わる前に次の相続が始まってしまった
相続が終わる前に相続人が死亡してしまったとします。
高齢の夫婦で年が近い場合は、妻が亡くなった後夫も後を追うように・・・と特に起きやすい事態だと言えます。
このように相続が重なることを数次相続といい、相続人が増えたりそれぞれの事情が複雑になるので遺産分割がまとまらなくなる可能性があります。
合わせて読みたい>>>数次相続とは?代襲相続・再転相続との違いや相続手続き・相続放棄の注意点を解説
例を用いて説明してみましょう。
母親Aが死亡して9,000万円の遺産を子B、C、Dの3人に遺しましたが、相続が終了する前に子Bが死亡してしまいました。死亡したBには妻Eと子Fがいます。
Bが相続を受けてから死亡した場合は、Bが受け取った3,000万円の遺産は妻Eと子Fに1,500万円ずつ受け継がれます。
しかしこの例ではBは相続終了前に亡くなってしまったので子CとDだけでなくBの妻EとBの子Fを交えて遺産分割を話し合う必要がでてきてしまいます。妻Eと子Fは叔父・叔母であるCやDをよく知らないかもしれませんし、夫のBを亡くして心細くより多くの遺産を主張するかもしれません。
対策としては早い段階で相続を終了させることです。
上記例であれば、最初の相続が円滑に終了してあればBが亡くなっても3,000万はEとFの手元に確実に残るので、当面の生活は安心だと言えます。
その為にも、遺産分割協議ではなく遺言を遺しておく必要があります。
遺言書がないと遺産分割協議が必要【相続手続の前提】
ここまでも触れてきましたが、そもそも遺産分割協議の必要がなければ、親族同士で争ってしまう可能性は非常に低くなります。
しかし遺言書がないと、相続手続を進めるためには遺産分割協議が必要です。(これは相続手続の前提です)
反対にいうと、すべての相続財産について遺言書で指定しておけば、遺産分割協議が不要なため、遺言があれば争族のリスクがだいぶ軽減されるということです。
遺言は故人の最後の意思表示として、相続においては最も重視されます。
もちろん遺留分という相続人の取り分を考慮しないといけないといった制約があるように、すべて遺言の通りに遺産を分けることができるわけはありませんが、基本的には遺言の内容に沿って相続は進みます。
また、相続人も故人が残してくれた遺言がそうなのであれば・・・と納得してくれる可能性も高くなります。
争族を避けるための遺言書作成のポイント
争族を避けるための遺言書作成のポイントとしては、次の3点が挙げられます。
- 公正証書遺言で作成する
- 税金や現金の配慮も遺言作成時にしておく
- 遺言執行者を指定しておく
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
公正証書遺言で作成する
遺言の種類としては主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は自分で書くことができるので敷居は低いですが、遺言の形式や要件を満たさないと無効になってしまいます。
より社会的信用が高い公正証書遺言を作成しておくのがベストです。
横浜市の長岡行政書士事務所でも、公正証書遺言の作成をサポートしています。
税金や現金の配慮も遺言作成時にしておく
遺言を書いたとしても思わぬ事態が生じて相続人に負担をかけてしまう可能性があります。
特に現金を用意する必要がある場合に注意が必要です。
例えば前述した換価分割では土地を相続した相続人は現金を準備する必要があります。不動産を売却すれば現金は準備できますが、相続人が高齢な場合は不動産の売却は大きな負担となります。
また、遺留分侵害請求も現金で支払う必要がありますが、遺言作成時に十分に配慮をしておかないと相続人は先妻の子といった思わぬところから急に遺留分侵害請求を受けて、現金の準備に困ってしまう事態にもなりかねません。
遺言作成時には専門家のアドバイスを有効活用し、可能な限りリスクを潰しておきましょう。
遺言執行者を指定しておく
さらに万全を期すためには、遺言執行者を指定しておくのもおすすめです。
遺言者の死亡後、遺言の内容を実現するために必要な行為を行うことを「遺言執行」といいます。
本来、遺言の内容の実現は、遺言者の権利義務を受け継ぐ人である相続人が行うべきともいえますが、遺言の内容によっては、相続人間で利害が対立する可能性があります。
このような場合、相続人自身による公正な執行が難しいことも留意しなければなりません。
また、たとえ相続人同士で利害が対立しないとしても、そもそも相続手続を相続人自ら行うことは、知識的にも精神的にも負担となります。
そこで遺言書で、「遺言執行者」を指定しておくのです。
遺言執行者とは、遺言執行の目的のために特に選任された者のことで、これを指定しておくことで確実に遺言内容を実現してもらえます。
横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言書の作成とあわせて、遺言執行業務にも対応しています。さらに詳しく制度について知りたいという方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
参考:遺言執行者とは?実行する内容・権限の書き方を行政書士が分かりやすく解説
横浜市の遺産分割準備は長岡行政書士事務所に相談!
家庭裁判所の統計を見ると、相続で家庭裁判所が調停を行った件の約75%が資産総額5,000万円以下の相続だという事がわかります。
相続でトラブルになるのはお金持ちの家に限ったことではありません。
どの家にも起き得る可能性があります。
また、普段仲の良い家族ほど相続がうまくいかないと「あんな奴だとは思わなかった」と関係が崩れてしまうケースも多いのが実情です。
あわせて読みたい>>>トラブルのない家族でも遺言を書くべきか?遺言を書くべき背景と理由を説明!
病院と同じように普段から相談ができる「かかりつけ」の法律家を持って、相続を含めた広範な法律のサポートを受けるようにしましょう。
長岡行政書士事務所は相続の経験が豊富にあり、相談者様に寄り添った相続を目指しております。
ご不明な点や不安がございましたら、是非当事務所にご相談ください。初回相談は無料で対応しています。