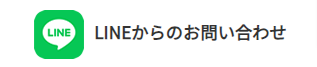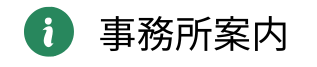「私の死後、お世話になったあの人に財産を譲りたい。」
「離婚した妻との間に子供はいるが、内縁の妻に全財産を残したい。」
「知人から遺贈したいと言われた。遺贈って何?メリット・デメリットを知りたい。」
生前とてもお世話になった人がいらして、家族ではないけれど、一部あるいは全ての財産を譲りたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続は一般的には法定相続人(※1)であるご家族に対して行われるものです。
※1法定相続人とは
特段の指定がない場合に適用される法律で定められた相続分のこと。
相続人に応じて、相続分は次の通り。
・配偶者と子の場合・・・各2分の1
・配偶者と父母の場合・・・配偶者3分の2、父母3分の1
・配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
しかし、生前に遺言書に明記しておくなど準備をすることで、ご家族以外の方にも遺産を渡すことが可能となります。
このように、法定相続人ではない方へ遺産を残すことを『遺贈(いぞう)』といいます。
そして、遺贈には『特定遺贈(とくていいぞう)』と『包括遺贈(ほうかついぞう)』という2種類があります。
この記事では、特定遺贈と包括遺贈との違いやメリットデメリットについて解説していきます。
目次
遺贈とは第三者に財産を受け継がせること
本来、相続において亡くなった人の財産を相続する権利があるのは『法定相続人のみ』となります。
法定相続人となることができる人は民法において定められており、遺言書がなければ法定相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産を分割することとなります。
合わせて読みたい>>遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説
もし、法定相続以外の第三者に受け継いでもらいたいとお考えの場合には、生前の意思表示として遺言書を遺す必要があります。
このように、遺言書によって亡くなった人の遺産の全部または一部を、法定相続人以外の第三者に対して遺産を贈与することを『遺贈』といいます。
遺贈は、婚姻関係にない内縁の妻や、法定相続人に含まれない孫、介護でお世話になった息子の妻などにも財産を残したい場合にも有効な手段です。
また、特定の第三者だけでなく病院や教育機関などの法人など、人以外の団体などであっても遺贈することが可能です。
合わせて読みたい>>遺産を団体に遺贈寄付したい時はどうすればいい?長岡行政書士に聞いてみた
遺贈において遺産を贈る側の人を『遺贈者(いぞうしゃ)』と呼びます。被相続人が遺贈者となります。
遺産を受け取る人のことを『受遺者(じゅいしゃ)』と呼びます。
遺贈と相続の違い
『遺贈』と『相続』は財産を譲るという意味ではよく似ていますが、財産を受け取ることができる対象が異なります。
『相続』は法律の規定に従って遺産が法定相続人に受け継がれることをいいます。
つまり、相続を受けることができるのは法定相続に限られています。
したがって、相続では相続人でない人に対して財産を受け継いでもらうことはできません。
仮に、相続人以外の人に対して遺言書で「相続させる」と記載した場合、無効となってしまう可能性があります。
一方、『遺贈』の場合は遺言書に記載があれば相続人でなくとも受け取ることができます。
つまり、遺言書に「遺贈する」と記載することによって被相続人との続柄に制限なく財産を受け継ぐことが可能です。
ただし、相続とは違って遺贈の場合は必ず遺言書を作成して遺贈したい旨を記載する必要があります。
『遺贈』とするか『相続』とするか注意が必要な場合
遺贈の場合、受遺者となる人に制限はない、つまり相続人以外の第三者に遺贈することも可能ですが、相続人が受遺者となることも可能なのです。
ただし、一般的に相続人には遺贈ではなく、相続する方がメリットがあるため、あえて遺贈をする必要はないと考えられています。
相続人を受遺者とするデメリットとして、例えば、土地や建物などの不動産を引き継いだ場合、相続であれば相続人単独で所有権移転の登記手続きが可能です。
しかし、受遺者であれば他の相続人全員と共同で申請をする必要があるため、手続きに手間がかかるおそれがあるのです。
一方で、相続人を受遺者とする場合、特定遺贈であれば相続放棄をしても受け取ることができるなどのメリットもあります。
遺贈と相続は財産を譲るという意味では似ていますが、利用する場面によってメリットデメリットがあるため、よく検討する必要があります。
遺贈と生前贈与の違い
『生前贈与』とは、生前に財産を誰かに無償で譲るという契約です。
遺贈も生前贈与も財産を譲るという意味では同じようですが、財産の移転時期や方法に違いがあります。
遺贈と生前贈与の財産の移転時期
『遺贈』は死後に財産の移転が行われるものです。
これに対して、『生前贈与』は被相続人の生前に贈与契約によって財産を譲り渡すものです。
したがって、『遺贈』の場合は亡くなった後に財産が移転し、『生前贈与』の場合には被相続人が亡くなる前に財産が移転するという違いがあります。
財産の移転時期が違うため、遺贈の場合は相続税の対象となり、生前贈与の場合には贈与税の対象となるといった違いもあります。
遺贈と生前贈与の方法
『遺贈』は単独行為であるため、相手方の同意も必要なく、被相続人の一方的な意思表示で行うことができます。
遺贈をしたい旨の意思表示は遺言書で行う必要があります。
また、遺言書が有効なものとして成立するためには厳格な決まりに従って作成する必要があるので、少し手間はかかると言えるでしょう。
一方、『生前贈与』は財産を譲る相手方の同意が必要となります。
ただし、生前贈与には厳格な書面作成などの要式性は必要なく、口約束であっても有効な契約となります。
特定遺贈とは
『特定遺贈』とは、遺産の中で財産を指定して指定して行う遺贈のことです。
数台あるうちの自動車1台を指定して特定遺贈とすることも可能ですし、A銀行の預貯金などある程度まとまったものであっても特定遺贈となります。
特定遺贈と包括遺贈の違い
さて、遺贈には『特定遺贈』と『包括遺贈』の2種類があります。
特定遺贈と包括遺贈の違いは、一言で表すと『相続人と受遺者が同一に近い権利義務を有するか否か』です。
『特定遺贈』は、先ほど紹介した通り、特定の財産を指定して遺産を相手方に受け継がせるものです。
特定遺贈は、特定の財産のみを受け継ぐことができます。
特定遺贈の受遺者は、特定の財産のみを受け継ぐため、相続人とは同一の立場とは言えません。
そのため、特定遺贈の場合には負債などを受け継ぐこともなく、遺言書に記載された財産のみを受け継ぐというシンプルなものです。
また、特定遺贈を受けたくない場合、特段の手続きは必要なく法定相続人に対して「財産は受け取りません」という意思表示をするだけで放棄することができます。
*特定遺贈の例
|
包括遺贈とは
一方、『包括遺贈』は遺産の内容を特定せず、全てあるいは遺産全体の何割、何分の何というように割合によって相手方に受け継がせるものです。
包括受遺者となった場合には相続人と同様に近い権利義務を有する立場になります。
そのため、包括遺贈の場合、負債などがあればその負債も指定された財産の割合に応じて引き継ぐことになります。
包括遺贈では負債も背負わないといけないということですから、場合によっては遺贈を受けると不利になってしまうということもあります。
負債の方が大きく、遺贈を受けることで不利になるといったような場合には、相続と同様に『単純承認(※2)』・『限定承認(※3)』・『相続放棄(※4)』をする権利が認められています。
※2 単純承認とは
被相続人の権利義務を全面的に承継することを承認して遺産を受け継ぐこと。
※3 限定承認とは
被相続人から受け継いだ財産の範囲内において被相続人の負債などを負担するという条件付きで遺産を受け継ぐこと。
※4 相続放棄とは
被相続人の権利義務について受け継ぐことを全面的に放棄すること。
包括遺贈の場合、財産を受け取る意思はないというような場合には家庭裁判所へ『相続放棄する旨の申述』を行う必要があります。
また、相続放棄ができる期間についても、『包括遺贈を受け取ったことを知った日から3ヶ月以内』に家庭裁判所へ申述する必要があると法律で定められています。
包括遺贈を放棄する場合には注意が必要です。
*包括遺贈の例
|
特定遺贈のメリット
特定遺贈のメリットとしては、次の3点が挙げられます。
|
財産と受遺者を具体的に特定できる
遺言は被相続人の意思を表すものであり、遺言によって示された被相続人の意思を最大限に尊重して遺産相続が行われるのが一般的です。
ご本人の意思表示として、遺言書により特定遺贈をしたい旨と、財産と受遺者が具体的に被相続人によって指定されています。
そのため、相続人との遺産分割協議など相続トラブルを回避することもでき、確実に特定の遺産を譲ることができます。
特定遺贈の「放棄」には期限がない
特定遺贈では他の相続人から遺贈を承認または放棄の催促がなされない限り、遺贈を受け取るか放棄するか判断する期限が設けられていません。
つまり、特定遺贈の受遺者は被相続人の死後、いつでも遺贈の放棄をすることができます。
放棄する方法についても、特段の要式性は求められません。
そのため、相続人と遺言執行者(※5)に対して一方的な意思表示、かつ口頭で行うことも可能です。
※5 遺言執行者とは
相続にあたって、被相続人が遺言を残している場合に、遺言の内容を実現させることを職務とする者のこと。
ただし、相続人などから遺贈を受け取るか放棄するか判断を求められた場合には、相当の期限が定められるはずです。
期限が定められると相続人の指定した期間内に特定遺贈の承認または放棄をしなければなりません。
期限内に承認または放棄の意思表示を行わない場合には自動的に遺贈を承認したものとみなされるため注意が必要です。
負債は引き継がなくていい
特定遺贈の場合、特定の財産のみを受け継ぐというものですから、遺言書に指定されていない限り、受遺者は被相続人が残した借金などの負債を受け継ぐ必要はありません。
例えば、被相続人が事業を経営しているような場合、借金があるようなケースでは事業に関わっていない人に対しては特定遺贈で財産を残しておけば負債を引き継がせることなく遺産を残すことが可能です。
特定遺贈のデメリット
特定遺贈にはデメリットもあります。特に下記のデメリットは覚えておきましょう。
|
遺留分侵害額請求の対象になりうる
遺言書に記載した内容が、相続人の遺留分を侵害している場合、法定相続人から遺留分侵害額請求権を行使される可能性があります。
特定遺贈を利用して相続トラブルを回避しようとしても、遺言書の内容によっては遺留分を侵害し、遺留分トラブルが起きるおそれがあります。
遺留分を侵害しない遺言書を作成したい場合には、行政書士などの専門家への相談もご検討ください。
合わせて読みたい>>遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説
法定相続人以外の人が不動産を受け取る場合は不動産取得税がかかる
被相続人の財産に不動産があり、その不動産を特定遺贈として取得する場合、相続や包括遺贈であれば不動産取得税は課税されませんが、特定遺贈だと不動産取得税が課税されます。
被相続人の財産に不動産がある場合、相続や包括遺贈であれば不動産取得税は課税されません。しかし、特定遺贈だと不動産取得税が課税されます。
不動産所得税とは、売買や贈与などによって、土地や建物など不動産を取得した場合に不動産を取得した人に一度だけ課税される税金です。
|
特定遺贈の場合、負債は引き継ぎませんが、取得することによって不動産取得税の課税対象となる場合もあるため注意が必要です。
特定遺贈は公正証書遺言を利用することがオススメ
遺贈は金額が大きい場合も多く、相続人の遺留分を侵害してしまったり、受遺者が納税しなければならないなどのトラブルも想定される可能性があります。
そのため、遺留分の配慮など専門的な知識や適切な対応が必要です。
遺贈は、第三者に財産を渡すという性質上、確実に遺贈寄付を実現するためにも、法的に有効性が高いとされる公正証書遺言を選択した方が良い場合もあります。
さらに、遺言書において遺言執行者を指定しておくと安心です。
遺言執行者は遺言の内容を実現することが職務です。
つまり、遺言執行者は遺言者の意思を尊重するために存在するのです。
したがって、確実に財産を特定の人や団体へ残したいと思う場合には遺言執行者を指定することも有効な手段です。
いずれの場合であっても一人で対応するとトラブルを招く可能性もありますので、行政書士などの専門家に相談しながら安全な方法で行うことをおすすめします。
そんな時は、長岡行政書士へ一度相談してみてください。
この記事もご参考ください:遺産を団体に遺贈寄付したい時はどうすればいい?長岡行政書士に聞いてみた
<参考文献>
・常岡史子著 新世社 『家族法』
・新井誠・岡伸浩編 日本評論社 『民法講義録』