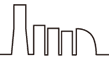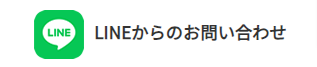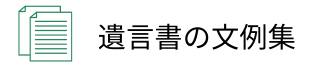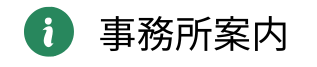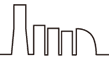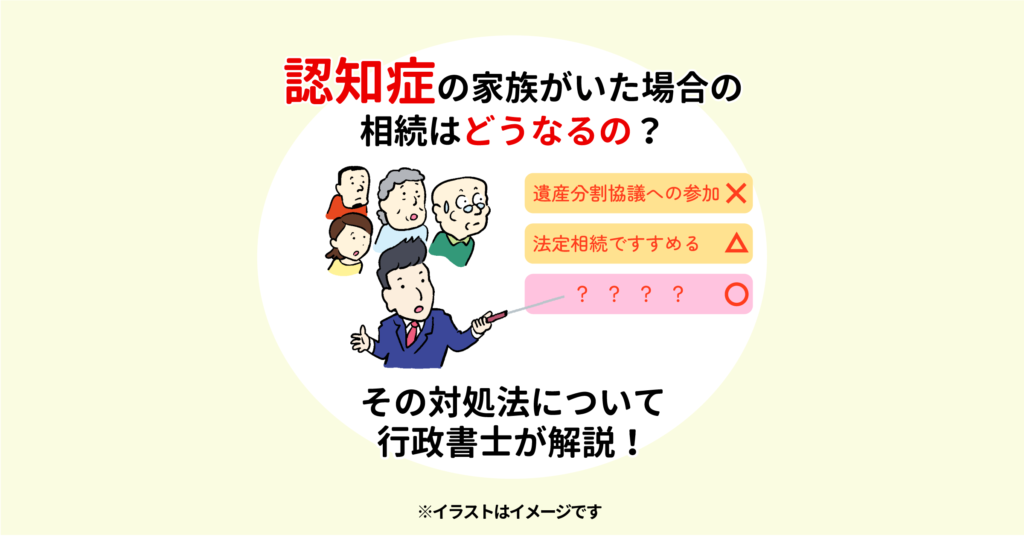
「認知症になった家族は相続を受けることができるのでしょうか?手続が面倒だと聞いたのですが、、、」
「法定相続人が認知症の場合、遺言書を書いておいたほうがいいのでしょうか?」
認知症とは様々な原因により記憶や思考といった認知の機能が低下し、日常生活や社会生活に支障が出ている状態の事を指します。
そして、認知症になると単独で契約を結ぶといった法律行為ができなくなります。
では、家族に認知症になった人がいる場合、その人は相続を受けることができるのでしょうか?例えばですが、認知症の母がいる家族で父が亡くなった、というような場合です。
お金を受け取るだけなら認知症になってもできそうだけど、そもそもお金を受け取ったことがわからないのではないか・・・
そもそも相続方法を決める話し合いに参加できるのだろうか・・・
そのような不安ももっともなものです。
法定相続人が認知症の場合、スムーズに相続手続を進めるためには遺言書を書いておくべきです。
この記事でいくつかポイントや注意点を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
相続は遺言書がある場合・ない場合で手続が異なる
まず前提として、相続は遺言書がある場合・ない場合で手続方法が異なります。
亡くなった方が遺言を遺してくれている場合は、基本的に相続の内容は遺言に従います。
例外として、財産を受け取る相続人全員が遺言とは別の分け方で合意した場合は遺言分割協議が優先しますし、また遺言とは別に法律で認められた遺留分という権利もありますので完全に遺言で相続の全てを決めることはできませんが、遺言は故人の最後の遺志として最も尊重されていると言えます。
そして、遺言がない場合は法律に則って遺産を分割する法定相続か、相続人全員が参加して遺産分割について話し合う遺産分割協議のどちらかを選ぶことになります。
合わせて読みたい:遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説
認知症になると遺産分割協議に参加できない
ここでまず問題になるのは、判断能力がない認知症の家族は遺産分割協議に参加することができないことです。
遺産分割協議は相続人全員で合意する必要がありますが、相続人のうちひとりでも認知症などで判断能力が低下していると遺産分割協議自体に参加することはできません。
つまり、遺産分割協議を完了させることができなくなります。
これは認知症の家族本人以外の相続人にとっても大変不便なことです。
故人が所有している金融機関に死亡の事実が知られると故人の口座遺産は凍結され、原則的に銀行預金はおろせず、不動産も処分できなくなってしまいます。
また、相続税の申告・納付期限は10カ月ですが、その期限までに遺産分割協議を終わらせないと相続税の申告・納付ができずペナルティが発生する可能性があります。
認知症の法定相続人がいる場合に遺言書を書くべき理由
ここまで紹介した前提をふまえると、法定相続人が認知症の場合に遺言書を書くべき理由としては、次の2つが挙げられます。
- 相続のために成年後見制度を利用する必要がなくなる
- 遺産分割協議書がなくても相続手続を進められる
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
相続のために成年後見制度を利用する必要がなくなる
相続人に判断能力がない認知症の人がいると遺産分割協議はできなくなり、相続を進めることが不可能になるのでしょうか。
実は1つだけ、認知症の方がいても遺産分割協議を進める方法があります。それは、成年後見制度を利用することです。
成年後見制度は、一人で法律行為をすることが不安、もしくはできなくなった人の為に、家庭裁判所が成年後見人を選んで本人を保護してくれる制度です。
具体的には、この成年後見人が本人に代わって財産管理や重要な契約を行ってくれます。
仮に本人が騙されて契約してしまったりしても、その契約は取消しすることができるので、本人の利益を守ることが可能です。
成年後見制度に関しては私が監修した書籍がありますので、よろしければ参考にしてみてください(成年後見制度がよくわかる本~長岡真也監修本出版のお知らせ~)
最初の例の通り、判断能力が無い認知症の母がいて、父が亡くなった場合を考えると、父が亡くなる前から母の成年後見人が選任されている場合には相続発生後に成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
一方、成年後見制度を母の為にまだ使っておらず父の死後急いで遺産分割協議を進めるために母の成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てた場合、手続きには3~4カ月ほどかかってしまいます。
相続税申告の期限は10カ月であることを考えると、あまり時間的に余裕はありません。
なるべく早めに成年後見制度を利用するかの検討を始めるべきでしょう。
このように、成年後見制度は本人の利益を守るための公の制度ですが、注意すべき点も存在します。
- 第三者の専門家が成年後見人となる可能性が高い
- 門家が後見人に選任されると報酬が発生する
成年後見人は本人の資産状況を把握したり、家庭内の事情も知る必要がある場合があります。
プライベートを考えると成年後見人に親族が選ばれてほしいと希望する方もいますが、ここ数年間の傾向では家庭裁判所によって成年後見人に選任される人は親族の割合は下がり、外部の弁護士や司法書士、行政書士といった専門家などの割合が増えています。
成年後見人に専門家が選ばれた場合でも人によっては親族と話し合いの姿勢をみせてくれたりする可能性はありますが、あくまでも成年後見人は本人の利益を守るべき存在なので親族の希望が通らない事があります。
例として、遺産分割協議において認知症の本人は高齢なのでもうお金も使わず、また十分に資産があるので子に多く残してほしいとの要望が他の相続人から出てきても、成年後見人は本人の利益を最優先で守るため法定相続分の遺産額を主張することになります。
本人が健在であれば子の為に多めに譲ってくれるのではと考えられる状況でも、成年後見人は職務としてそのような融通をきかせることはできないのです。
また、専門家が後見人に選任されると報酬が発生します。
あくまでも目安ですが、月2万円から財産額によっては月5~6万円になることもあります
さらに、成年後見制度は原則として途中で中止することができないので、後見を受ける本人が亡くなるまで報酬が発生します。
長い目で見ると親族にとって経済的な負担となる可能性があります。
このように、成年後見制度を利用して遺産分割協議を進めることには、デメリットも少なからず存在するのです。
しかし遺言書を用意しておけば、遺産分割協議の必要がありません。そのため、たとえ認知症の相続人がいても、成年後見制度を利用せずに相続手続を進められます。
そのため法定相続人の中に認知症の方がいる場合には、遺言書を用意しておいたほうがいいのです。
遺産分割協議書がなくても相続手続を進められる
遺言がない場合、不動産の相続登記の相続手続を行う場合であれば、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
しかし、それ以外の財産の手続であればやはり各相続人の同意が必要であり、この場合、判断能力がない認知症の相続人は自分の適正な意思が表示できず、相続手続が止まってしまいます。
ここまで読むとでは判断能力がない認知症の家族がいたときにおいて、不動産の相続の場合は、法定相続ですすめればいいのではと思われるかもしれませんが、実務的には問題があります。
不動産は、法定相続で分けるという事は一つの土地や家を相続人で共有することになります。遺産分割協議書が必要なく相続登記ができたとしても、不動産が共有状態であれば単独で売却や賃貸を行うことができず、資産として活用することができません。
更に「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減」といった相続税を抑える特例も、遺産分割協議ができなければ利用できません。
このような不都合を防ぐためにも、法定相続人の中に認知症の方がいる場合には、やはり遺言書を用意しておいたほうがいいのです。
法定相続人の中に認知症の方がいるなら遺言書の用意を!
このように、判断能力がない認知症の家族がいる場合であっても、遺産分割協議や不動産の場合は法定相続といった方法で相続を進めることができます。
しかし、どちらも故人の気持ちや相続人の利益に完全に寄り添ったものとは言えません。
一方、遺言を作成しておけば、認知症の家族がいても、遺産分割協議や法定相続をせず相続手続きを進めることができます。
そのため、たとえば配偶者が認知症になっている場合などは、ぜひ遺言書の作成を検討してみてください。
横浜市の長岡行政書士事務所は、遺言書作成をサポートした経験が豊富にあり、状況に応じたご提案をすることが可能です。
遺言書作成にあたって不安や疑問点がある場合は、是非お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。