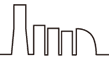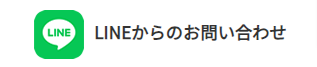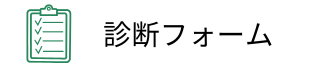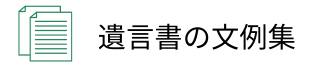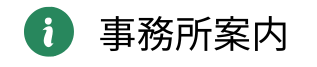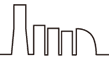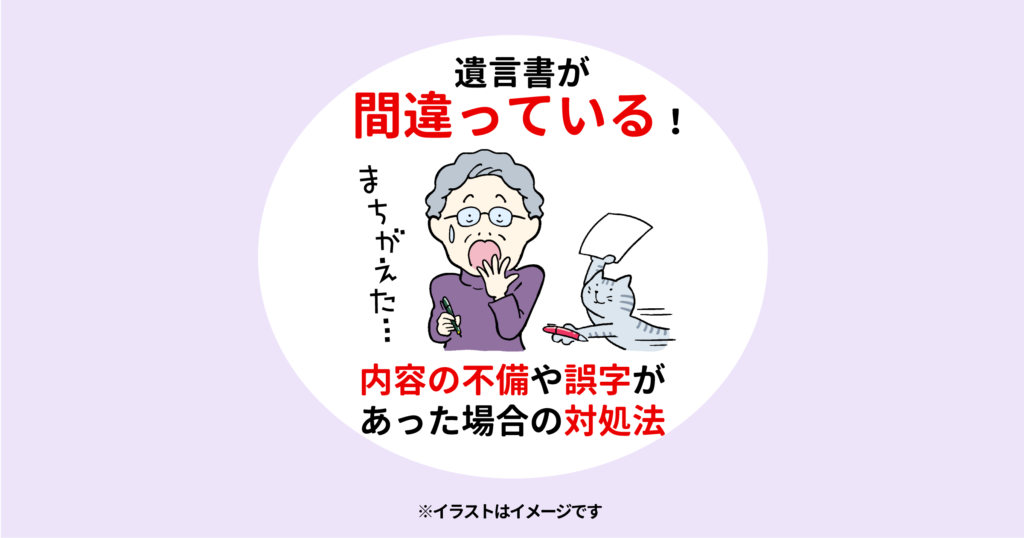
「公正証書遺言を作成したのに内容を間違えた!どうしよう?」
「出てきた遺言書が間違えている・・・大丈夫?」
「遺言書の口座番号が間違えているけど、その口座の財産は相続できない?」
遺言書は、ご自身がお持ちになっていた財産を「大切な誰かに残したい」という大切な最後の意思表示です。
その遺言書に間違いがあった場合どうなるのでしょう?
遺言書の方式は、法律で厳格に定められています。
その決められた方式に従っていない場合には効力が生じないとされています(民法960条)。
遺言の効力は遺言者が亡くなってから生じます。
つまり、遺言の内容によって遺言者の意思を判断する以外に方法がないのです。
だからこそ遺言者の意思を確実に実現するために遺言書の方式に厳格なルールが求められています。
しかし、人間ですから誰しも間違いはありますよね。そのため、遺言内容の不備や、遺言書に誤字がある場合もあります。
でも大丈夫です!遺言書が間違っている場合の対処法も存在します。
今回は遺言書を間違えてしまった場合の対処法についてお話ししたいと思います。
目次
遺言書は訂正できる
遺言書が間違っている場合、訂正はできます。
ただし、訂正方法は遺言書の種類や、誤っている内容・程度によって異なります。
そのため、遺言書を訂正した場合、「訂正したい遺言書の種類」「どのような内容を、どう訂正したいのか」を判断しなくてはなりません。
ここからは、遺言書の種類と訂正方法について、それぞれ解説します。
遺言書は2種類
『遺言書』と一言で言われがちですが、遺言書には一般的なものとして「自筆証書遺言」と、「公正証書遺言」の2種類の遺言書があります。
まず、その遺言書の種類についてそれぞれご説明します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の『全文』、『日付』、『氏名』を自分で書き、『押印』するという方式のものです(968条1項)。
自筆証書遺言は証人や立会人を必要とせず、遺言者一人で書くことができます。
しかし、一人で書けるからこそ自筆証書遺言には厳格なルールが定められています。
これは遺言者の最終意思の確認を確実にするためです。
ただし、そのルールが厳格になりすぎてしまうと遺言が簡単に無効となってしまいます。
そこで、平成30年の法改正によって一部自筆証書遺言の方式が緩和されました。
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言の要件は、遺言者が遺言書の『全文』、『日付』、『氏名』を自分で書き、『押印』するという方式だと紹介しました。
ただし、そのルールが厳格になりすぎてしまうと遺言が簡単に無効となってしまいます。
そこで、平成30年の法改正によって一部自筆証書遺言の方式が緩和されました。
平成30年の法改正によって、自筆証書遺言に添付する『財産目録』については手書きの必要がなくなったのです。
例えば、パソコンで作成した財産目録を別紙として不動産の番地、預金の金融機関と口座番号などのリストを添付するということができます。
この財産目録のリストにはページごとに署名、押印は必要となりますが、その他には特段の要式性は求められません。
したがって、『パソコンなどによる作成』はもちろん、『他の人による代筆』、『不動産の登記簿証明や預金口座の写し』などを添付するということも可能です。
合わせて読みたい>>遺言書の書き方・方式・注意点を行政書士事務所の事例と共に解説!
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人の前で遺言を口頭で伝え、それに基づいて公証人が遺言の内容を文章化して作成される遺言書のことです(969条)。
合わせて読みたい>>公正証書遺言は自分で作れる!実際の作成方法や流れを行政書士事務所が解説
公正証書遺言の要件
公正証書遺言の要件は、次の6項目です。
- 証人2人以上の立ち会いがあること
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えること
- 公証人が、遺言者から伝えられた内容を筆記すること
- 公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧せること
- 遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと
- 公証人がその署名は上記①〜⑥の方式にしたがって作ったものである旨を記入し、これに署名、押印すること
この6つの要件が揃っていなければ公正証書遺言も無効とされます。
公正証書遺言の作成には専門家である公証人が関与するため、形式の不備によって無効となることは稀なことと思います。
遺言書の訂正方法
遺言書の訂正といっても遺言書の種類によって変わることはもちろん、間違えた内容がそもそも遺言の内容を間違えたのか、誤字なのか、その訂正内容によっても訂正方法が変わります。
ここからは、遺言書の訂正方法を、訂正したい内容と遺言書の種類に合わせて解説します。
遺言書の内容に間違いがあった場合の訂正方法
まず遺言書本文の内容に間違いがあった場合について見ていきます。つまり中身が間違っていた場合です。
誤字脱字の場合と違いますので正確に把握しておきましょう。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言の内容に間違いがあった場合、訂正箇所を正しい内容に書き加えたり訂正するためには、遺言者がその訂正箇所を指示し、これを変更した旨を書き加えます。
さらに、変更した場所に押印しなければ変更した内容は無効となります(968条)。
| 〜チェックリスト〜 |
|
自筆証書遺言の訂正箇所を指示する際は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印を訂正箇所の二重線の近くに押します。
訂正前の文字が見えるようにしておくと良いです。
訂正印は署名の横に使用した印鑑と同じものを使用してください。
自筆証書遺言はご自身だけで用意できるものです。
訂正する場合も要件に適合していない場合、無効となるおそれもあるため、自筆証書遺言を間違えてしまった場合は書き直すことがベターだと思います。
合わせて読みたい>>自筆証書遺言書の正しい書き方|失敗例から注意点を学ぼう!
公正証書遺言の場合
すでに公証役場に保管されている公正証書遺言の内容に間違いがあった場合には、遺言書の原本を差し替えるのが一般的です。
その際は最初の公正証書遺言の手続きと同様の要件のもとに作成していくこととなります。
発行から3ヶ月以内の印鑑登録証明書や印鑑を持参して、公証人と立会人2人以上が同席のもと、前回の遺言書の内容を撤回する旨を伝えて署名捺印する必要があります。
新たな公正証書遺言書の中に作成年月日を記載し、前回作成した年月日とその遺言書の内容を撤回する旨を記すことで遺言書の内容変更をすることができます。
手間もお金もかかるしもう二度と公正証書遺言は作りたくない!という場合には、自筆証書遺言をおすすめします。
前回の遺言書と種類が異なっていたとしても新しい遺言書の効力は生じます。
| 〜チェックリスト〜 |
|
誤字など軽微なミスの訂正方法
次に、誤字脱字、内容の軽微なミスの場合の訂正方法はどうなるのでしょうか。
誤字の訂正方法も、遺言書の種類にあわせて確認してみましょう。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言の記載内容から誰が見ても明らかな誤記については、書き加えたり除いた場合や、変更について決められたルールに従っていない場合であっても、遺言の効力には影響はないと認められています。
これは、些細な方式の違反を理由に遺言者の最終意思の実現を妨げることは妥当ではないと考えられているからです。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言に誤字脱字などの間違いがあった場合、例えば公正証書遺言に記載されていた不動産の所在地と登記簿記載の所在地が異なっていた場合には、同一の不動産として認定してもらうことができない可能性があります。
つまり、誤記のまま申請すると相続手続きを進めることができない場合があります。
公正証書遺言の内容そのものに変更はないけれど、軽微な誤字脱字や誤記がある場合、「誤記証明書」を発行してもらうことで対応可能です。
「誤記証明書」の発行には、必要書類や公正証書遺言を作成する場合のような手続きも必要ありません。
誤記証明書は公証人に作成してもらうことができます。また、費用はかかりません。
誤記証明書は公証人が誤記部分を特定し、正しい記載内容とその根拠となる資料を記載し、署名捺印をして作成します。
公正証書遺言の誤記を見つけた場合には必ず誤記証明を受けてください。
ご自身で直接訂正してしまうと偽造・変造にあたります。注意してください。
なお、誤記証明書で訂正可能なものは、明確な誤記などに限られます。
つまり、公正証書遺言の付属書類や戸籍謄本などの関係書類、あるいは公正証書遺言の他の記載部分と照らし合わせて誤記が明らかな場合に限られます。
事前に提出した書類などに誤りがあった場合など、何でも訂正できるわけではないため注意が必要です。
大きな間違いであれば改めて遺言書を作成する
遺言者個人の意思で、遺言書を変更または訂正をすることは可能です。
そもそも遺言は、遺言者の最終意思に対して法が効力を与えてその意思を保護しようという目的のもとに制定されています。
遺言者の意思を保護するという趣旨ですから、遺言者は撤回する権利を放棄することもできません(民法1026条)。
したがって、生存中であれば遺言者はいつでも何度でも遺言を撤回することも自由です。
しかし、すでにお話しした通り、軽微なものであれば訂正は可能ですが、内容などの大きな間違いであれば改めて一から書き直すこととなりますので一度遺言書を撤回することになります。
遺言書の内容を消滅したい場合は「遺言書を撤回する」旨の遺言書を作成
遺言を撤回する場合、通常はすでに作成されている遺言を撤回し、新たな遺言書を作り直すことが想定されています。
この場合は、新たな遺言の中で前の遺言を撤回する旨を記載することで遺言の撤回をすることができます。
では、一度作った遺言書を撤回して、そもそも遺言書の存在自体をなくしたいという場合にはどうするのでしょうか?
遺言書を作ったけど、遺言書はもう作りたくない、そんな時でも自筆証書遺言でも公正証書遺言でも撤回はできます。
しかし、遺言書の内容を完全に消滅させることはできても遺言書の存在自体をなくすことはできません。
この場合、自筆証書遺言の場合であっても、公正証書遺言の場合であってもそれぞれの形式に従って「今まで書いた遺言を撤回する」という旨の遺言書を作成し直すことになります。
つまり、「すでにある遺言書を撤回します」という趣旨の新たな遺言書を作成することになります。
遺言書は作るのも訂正するのも大変|行政書士へ相談を
財産状況の変化や、家族の状況など生活が変化することも想定されるため、遺言書は定期的に見直すのが理想的とされています。
そして、ご自身の意思を残す手段である遺言書は、より確実な方法で残すことが大切です。
せっかく残していたとしても無効とされてはどうしようもありません。
一度遺言書を作成し、撤回や訂正をする場合には前回作成した遺言書と同じ種類である必要はなく、自筆証書遺言を書いたけど公正証書遺言で作成し直すことも可能です。
遺言書の訂正や撤回することをめんどうと思うかもしれません。
しかし、めんどうだからと言ってそのまま放置しておくと、真意でない遺言証書が有効なものとして現実のものとなってしまいます。
「これから遺言書を作りたいけど間違いがあったときも含めて心配・・・」など遺言書についてお困りの際は一度長岡行政書士事務所に相談してみませんか?
相談者様の意思に添えるように、ご安心いただけるように、精一杯ご協力させていただきます。
<参考文献>
・潮見佳男著 有斐閣 『民法(全)』
・新井誠・岡伸浩編 日本評論社 『民法講義録(改訂版)』
・常岡史子著 新世社 『家族法』