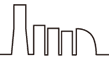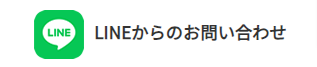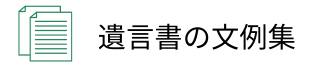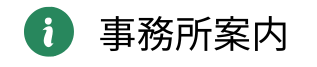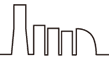「父が亡くなったときに相続登記しなかった不動産があるのですが、、、これも私の遺言書に書いていいのでしょうか。」
不動産の相続登記は 義務化されましたが、現実問題として、「自分の親が亡くなった時に、実家の相続方法を決めなかった」「実家の相続方法を決めなかったから、相続登記もしていない」という方もいるのではないでしょうか。
このように相続発生時にきちんと分割されないままになっている不動産を「未分割の不動産」といいます。
さて、相続登記していない不動産の所有者は、登記簿上は亡くなった方になっていますが、これを自分の遺言書に「自分の相続財産」として書くことはできるのでしょうか。横浜市で遺言書作成をサポートしている行政書士が、詳しく解説します。
目次
未分割の不動産とは?
そもそも「未分割の不動産」とはどのようなものなのか、理解を深めるため、例を用いて説明させてください。
夫A、妻B、長男C、次男Dの4人家族がいて、財産は実家である家だけ、長男Cはまだ実家に住んでいるが次男Dは家を出ているとします。
夫Aが亡くなりましたが、相続人が家族のみであり財産が家しかなかったこと、また次男Dが遠方に住んでいたため「なんとなく」そのままにしてしまいました。
実際に家には妻Bが住み続けており長男Cも同居を続けていたので表面上はなにも変わりませんが、実際は家は夫Aが亡くなった時にきちんと分割されておくべきでした。
どのように分けるかは遺産分割協議にて相続人同士の合意で決めることができますし、法律に則って分割する法定分割という方法もあります。
この例で法定分割をすると家の持分は妻Bが4分の2,長男Cが4分の1、次男Dが4分の1となりますが、遺産分割協議も法定分割も行われませんでした。当然、相続登記もしていません。
こらが「未分割の不動産」という状態です。
「未分割の不動産」も遺言書に記載できる
「未分割の不動産」であるマイホームに暮らしていましたが、妻Bは自身の体調に不安を感じ、遺言書を書くことを思いつきます。
具体的には、同居して自分の面倒を見てくれている長男Cに家をそのまま譲り、遠方で独立している次男Dには申し訳ないが何も残せない・・・と考えているのですが、そもそも完全に自分のものではない未分割の不動産を遺言書に書いても問題はないのでしょうか?
結論から言うと、遺言書に書いて相続させることは可能です。
相続ではお金や不動産といった目に見える財産以外にも、遺言を遺した人(=被相続人)の権利義務も相続人に受け継ぐことになります。
つまり「遺産分割をしていない状態の相続人である妻Bの地位」も、遺言によって長男Cに受け継がせることができるのです。
「未分割の不動産」を遺言書に書くときの注意点
さて、「未分割の不動産」を遺言書に書くときの注意点としては、次の2点が挙げられます。
- 「相続人としての地位をを相続させる」と記載する
- 遺留分に注意する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
「相続人としての地位をを相続させる」と記載する
「未分割の不動産」がある場合、あくまでも「不動産そのもの」ではなく、「遺産分割をしていない状態の相続人としての地位」を相続させることになります。
よって、遺言書には単に「家を長男Cに譲る」、と書くよりも、「遺言者である妻Bは死亡時に有する家の相続人としての地位を長男Cに相続させる」などと書くべきです。
遺留分に注意する
「未分割の不動産」を遺言書に書くときには、遺留分にも配慮すべきです。
遺留分とは、亡くなった人の法定相続人(兄弟姉妹以外)に保障されている、遺産の取り分のことです。
先述した例では、次男Dにも最低限の遺産を相続する権利(遺留分)があります。
そのため、もし次男Dが遺留分を請求した場合、家を譲り受けた長男Cは、現金で次男Dにも遺留分を払う必要が生じてくる可能性があります。
あわせて読みたい>>>遺留分とは何か?遺留分の割合と遺留分侵害請求について解説!
もしくは、長男Cも家を受け継ぐことにこだわらないのであれば清算型遺贈といって家を売却しその代金を長男Cと次男Dの間で分割する方法もあります。
この場合妻Bが遺言で家を長男Cに譲ると書いてあっても、実際の相続人である長男Cと次男Dが合意すれば清算型遺贈に変えることが可能です。
あわせて読みたい>>>清算型遺贈とは?押さえておきたいポイントを行政書士が解説
いずれにしても、「未分割の不動産」を相続させない人の立場を考慮することも重要なのです。
不動産の関わる遺言書作成は専門家に相談すると安心
この例では簡素化するため夫A、妻B、長男C、次男Dの4人家族しかおらず財産も家だけ、と設定しましたが、実際は相続人も遺産も多岐にわたる可能性があります。
また、夫Aから妻Bまでの2回の相続を考えましたが、相続自体が何回も重なると数代前の不動産は相続人だけでも何十人にも上り、また各地に相続人が散らばって存在してしまうこともありもはや収拾がつかなくなってしまいます。
さらに不動産は価値の大きな財産であるため、しっかりと遺言書に相続方法を記載しておいたほうが安心です。
しかし「不動産そのものを相続させる」と記載するのか、「不動産の相続人としての地位を相続させる」と記載するのかは、状況によって異なります。そのため不安なことがある場合は、まずは専門家に相談してみてください。
長岡行政書士事務所は相続・遺言書作成の経験が豊富にあり、御相談者様に寄り添った相続を目指しています。
ご不明な点や不安がございましたら、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。