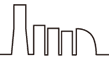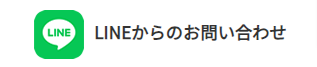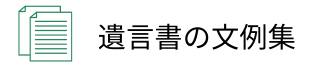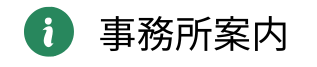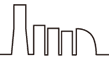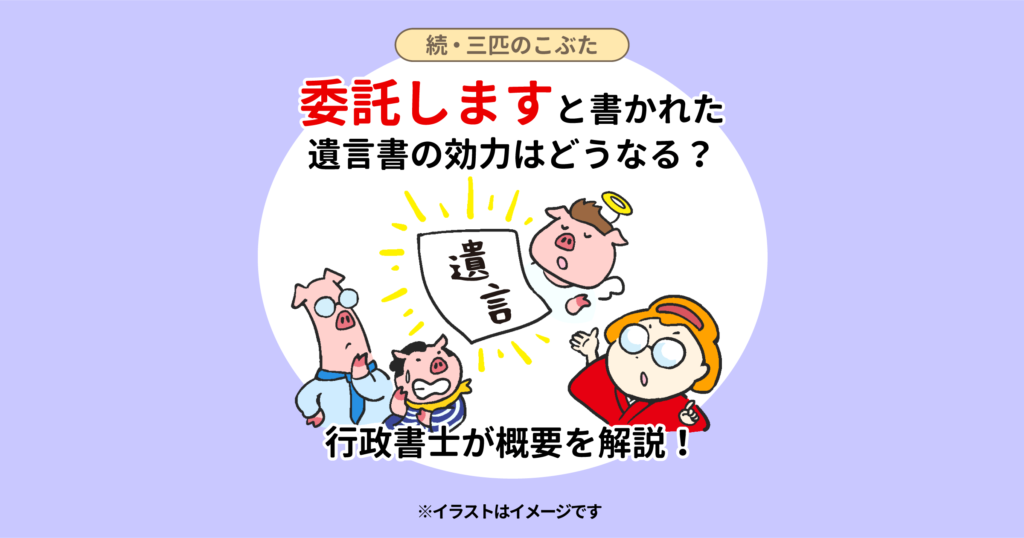
自分が亡くなった後、特定の人に自分が決めたとおりに財産を渡したい場合は、遺言書を書く必要があります。
しかし、遺言書を作成するとき、不明確・曖昧な言い方をすると効力が生じないこともあるため注意しなければなりません。
しかし遺言書において、不明確・曖昧な言い方とはどのようなものなのでしょうか。たとえば「相続させる」なら明確ですが、「委託します」はどうでしょう。
今回は曖昧な言葉で書いた遺言書の効力がどうなるかを、分かりやすく「童話風」に解説していきます。これから遺言書を作成しようと思う方は、ぜひ最後までご覧ください。
むかしむかし、あるところに三匹のこぶたがいました。石の家、木の家、ワラの家をそれぞれ作って育った兄弟ぶたたち。
隣村に住む赤ずきんちゃんと漁師さんの協力もあり、自分たちを罠にはめようとしたオオカミを見事に撃退!
その後、行政書士の資格を取得した赤ずきんちゃんたちに、遺言のさまざまなことを教えてもらいながら、幸せに暮らしていました。
そんなある日のこと。
兄ぶた「ねえねえ、赤ずきんちゃん。ひとつ質問していいかな?」
赤ずきん「もちろん」
兄ぶた「遺言書の言い方があいまいで、いくつかの意味に解釈できるような場合はどうなるんだい?」
赤ずきん「それではまず遺言書のおさらいからしていきましょう」
目次
遺言の内容が曖昧・不明瞭だとどうなる?
そもそも遺言書は、亡くなる方の最終の意思表示の効果として、遺産相続で一番優先されるものになります。
赤ずきん「遺言書は遺言者の最終の意思の効果。これはみんな知ってるわよね?」
弟ぶた「そうだよね。じゃないと書く意味なくなっちゃうし」
末っ子ぶた「それこそ仁義もへったくれもねえってもんでさあ」
兄ぶた「赤ずきんちゃん、ごめんね。末っ子はこないだ『清水の次郎長』の映画を見て、感化されてんだよね…」
赤ずきん「シブ(笑) まあ、仁義どうこうより、遺言書がないと遺産分割協議をすることになるから、なかなか大変なのよ」
弟ぶた「それ、確か、相続人が全員参加して遺産の分け方について話し合うって協議だよね」
赤ずきん「そう。全員の合意が必要になるから、ひとりでも欠けたらアウトね。そして、必ずしも故人の遺志が反映されるとも限らないわ」
しかし遺言書があれば、基本的にはその内容に沿って相続手続を進めることになります。そのため自分が亡くなった後、特定の人に自分が決めたとおりに財産を渡したい場合には、遺言書を書く必要があるのです。
ただし遺言書が残されていても、その文言が「不明瞭」だと、故人の意思と違う方向に進んでしまうかもしれません。
また、文言の解釈をめぐって争いがおき、せっかく遺してくれた遺言の意味がなくなってしまうかもしれません。
とくに自分で作成する『自筆証書遺言』の場合、「任せる」とか「委託する」などのあいまいな言い方をしてしまうケースはよくあります。(任せる・委託するは、遺言書においては曖昧な表現なのです)
遺言の内容が曖昧・不明瞭な場合、次のような事態が発生します。
- 遺言書の効力は有効
- 遺言書が指示していることについて争いが生じる可能性があ
遺言書の効力は有効
弟ぶた「もし任せる・委託するって遺言書に書かれていたら、遺言書は無効になってしまうの?」
赤ずきん「いや、遺言書が有効と認められる要件さえ満たしていれば、任せる・委託するなどと書かれているからといって、遺言書が無効になってしまうことはないわ」
遺言書が指示していることについて争いが生じる可能性がある
赤ずきん「でも、遺言書は無効にならないけど、一つてえへん(大変)なことがあるわ」
末っ子ぶた「なんでえ? 姐さん?」
兄ぶた「誰が姐さんや」
赤ずきん「それこそ、遺言書に書かれている任せる・委託するという文言の解釈が違うと、争いになってしまうこともあるの…」
末っ子ぶた「出入りですかい、姐さん?」
赤ずきん「めったなことを言うもんじゃないよ、森の石松。これ以上、ホトケさんを増やしてどうするってんだい」
弟ぶた「赤ずきんちゃんまでノリノリになってきたよ…」
兄ぶた「ふたりとももういいから…」
赤ずきん「ごめんね、ちょっと楽しくなっちゃった(笑)でもまあ、争いは起こしたくないわよね。遺言は本人の死亡によって発効するから、遺言書の文言の意味を本人に聞くこともできないからね」
弟ぶた「任せると書いたのなら、任せた結果を尊重するってことじゃないのかい?」
赤ずきん「でもね。遺産をあげるという意味なのか、それとも遺産分割の手続きを任せるという意味なのか、文面だけでは判断できないでしょ」
弟ぶた「確かに」
赤ずきん「当然遺産をもらえると思っている相続人がいたら、これは遺産をあげるという意味だと主張するよね」
兄ぶた「でもそうではない人は、単に遺産分割の手続きを任されただけと解釈してもおかしくない」
赤ずきん「そう。どう分けるかは話し合いによるべきだと主張するでしょうね」
末っ子ぶた「でも最終的には、話し合いでうまく決着がつけられればいいじゃないか。なんだか大げさだなあ」
赤ずきん「でも実はこれにはもうひとつ落とし穴があるのよ」
兄ぶた「…なんだい、こわいな」
赤ずきん「争いがあったり、争いになりそうな遺言書の場合は、後々のトラブルを恐れて金融機関が本人名義の預金を解約してくれないかもしれないの」
弟ぶた「ひゃー、それ大問題じゃん!」
遺言書の「委託する」という文言で争いになったケース
不明瞭な遺言により争いになり当事者間で解決が難しい場合は、裁判所に判断を仰ぐことになります。過去には、遺言書の文言のみで判断せず、前後の文との関係や遺言書作成当時の本人の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を総合的に判断すべきとの判例が出ています。
赤ずきん「例えばこんなケースが想定できるわ。あくまでフィクションだけどね」
- 兄ぶたが「預貯金を弟ぶたにすべて委託する」という内容の自筆証書遺言を作成した
- 兄ぶたの死後、弟ぶたは遺言書をもって兄ぶたの預金口座がある銀行で預金解約しようとした
- しかし、銀行の判断は「解約、NONONO!」、「ちょ、待てよ」と頭を抱える弟ぶた
- 銀行は他の相続人から「何でこの遺言でBに預金を支払ってしまったのか」とクレームが来て紛争に巻き込まれることを恐れた
- 「そんなの関係ねえ!」と弟ぶたは、「預金を支払え」という判決を求めて裁判所に訴えを起こした
弟ぶた「なんだか、ぼく、どんなイメージなの…?」
赤ずきん「フィクションだから、フィクション(笑)」
兄ぶた「で、裁判ではどうなったの?」
赤ずきん「そもそも委託って、一般的には人に頼んで代わりにやってもらうことという定義だよね。ってことは、預貯金の清算をやってもらうという解釈もできれば、預貯金を自分で取得してもよいと解釈もできる」
末っ子ぶた「言葉って難しいよね」
赤ずきん「遺言書の中には具体的にどういう事をやってもらいたいかの記載はないので「代わりにやってもらう」だけだと解釈するのは強引でしょ」
兄ぶた「そうだね」
赤ずきん「ここで、兄ぶたさんと弟ぶたさんの関係性が問題になってくるのね。遺言書作成当時、兄ぶたさんは弟ぶたさん以外の相続人と疎遠だった。え、弟ぶたさんに生活の面倒を見てもらっていたから、「弟ぶたに財産を残したい」と話していた」
末っ子ぶた「おいらだって、そばにいるぞ!」
赤ずきん「本当はね、たとえ話よ」
兄ぶた「裁判所はその関係性も考慮して判決を出したということだね?」
赤ずきん「そう。裁判所は、兄ぶたさんの真意は、弟ぶたさんに預貯金を遺贈することだとわかると判断して、銀行に預金支払いを命じたの」
弟ぶた「じゃ、任せると書いたケースでも、似たような解釈違いが起きることもあるわけだね」
明確な意味の遺言書を作るためにも専門家に相談する
赤ずきん「相続人の関係性にもよるけど、遺言書の文言が不明瞭だと、どんなトラブルが起きるかわからないわ。だから遺言書を作るときは、ちゃんと相続する・遺贈するなど専門的な言葉で書かなくちゃいけないの」
兄ぶた「ちゃんと書くといっても、言葉選びを間違えないようにするのも大変だなあ」
赤ずきん「そうならないように、行政書士など遺言書の作成をサポートしてくれる専門家に相談することが重要ね。行政書士と一緒に遺言書の草案を作ってから、それを公証役場に持ち込むようにすれば、自分の意思がしっかり反映された公正証書遺言を作成することができるわ」
横浜市の長岡行政書士事務所でも、遺言書の作成・遺言執行を承っております。自分の遺志を正確に反映した遺言書を残したいと考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料で対応しています。