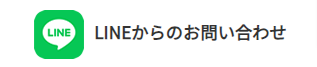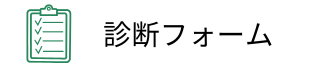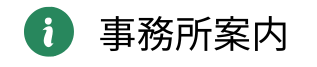「結婚するときに親から資金援助を受けたけれど、相続時にどうなるの?」
「亡くなった人の財産は、そのときに存在している財産だけなの?」
「生前資金援助を受けた兄弟が相続時同じ取り分なんて不公平では?」
結婚や住宅の購入など、人生の折々では大きな金額のかかるイベントがありますが、そのような時、ご両親から金銭的な援助を受けたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
または、そのような大きなイベントではなくとも、ご両親の生前、何かしらの生活資金の援助をうけたことがある、という方もいらっしゃるかもしれません。
そのような資金の援助は自分の財産を譲るわけですから、生前贈与にあたります。
ご両親から生前この贈与を受けていた場合、相続時にその受けた贈与はどのように扱われるのでしょうか。
今回の記事では、生前に受けた贈与と相続の関係について説明したいと思います。
目次
生前贈与と相続財産の関係
相続では、亡くなった人の財産を相続人で分割して受け取ることになります。
どのように分割するのかは、法律の定めに則った法定相続や、相続人間で話し合って決める遺産分割協議がありますが、いずれにしても、相続人の持ち分は亡くなった方(以降、被相続人といいます)の財産をもとに決められます。
合わせて読みたい>>遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説
分割するもととなる「被相続人の財産」がどのくらいあるのか判断する時、生前贈与されたされた財産と相続財産との関係はどうなるのか見てみましょう。
例えば、被相続人甲に、A・B・C3人の子どもがいる場合で、次のような生前贈与があったとします。
- Aに結婚資金として100万円援助していた。
- Cに住宅購入資金として500万円援助していた。
遺産分割の際、もし上記のよう生前贈与がなければ、甲の財産は実際よりも600万円多かったことになります。
そうすると、援助したことによって亡くなった時の財産は600万円少なくなっており、それをもとに取り分を計算したのでは、何も援助を受けていなかったCや、Cよりも援助額の少なかったAなど、相続人間で不平等が生じます。
そこで出てくるのが「特別受益」と「特別受益の持ち戻し」という考え方です。
特別受益とは
特別受益については、民法第903条で定めがあります。
民法903条1項(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
参照URL:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
特別受益とは、相続人の中に被相続人から生前贈与や遺贈を受けた者がいる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のことをいいます。
この特別受益がある場合、相続開始の時に実際に残っている相続財産の額に特別受益分を合算して遺産分割を行うことになります。
つまり、被相続人の手元からなくなっていた特別受益分の財産が相続財産に含まれるものとして扱われますから、その分、相続財産は多くなることになります。
そして、特別受益を受けた相続人の相続分は、特別受益分を加算した相続財産から各相続人の相続分を計算し、そこから受け取った特別受益分を差し引きします。
これを「特別受益の持ち戻し」と言います。なお、相続人間の合意によって持ち戻しを行わないようにすることもあり得ます。
この規定は、特別受益があった場合の相続人間の不平等を解消し、公平を確保するための定めと言えます。
特別受益に該当する贈与の種類
被相続人が生前贈与などをしていた場合、特別受益としてその贈与分が相続財産に加算されるわけですが、全ての生前贈与が特別受益とされるわけではありません。
特別受益にあたるものは、民法第903条第1項では次のように定められています。
- すべての遺贈
- 以下のいずれかの贈与
・婚姻のための贈与
・養子縁組のための贈与
・生計の資本としての贈与
遺贈とは、遺言書によって他人に財産を渡すことをいいます。遺贈によって財産を受け取った場合は、すべて特別受益の対象となります。
養子縁組のための贈与とは、養子縁組に出す際に実親が持参金を贈与するような場合のことで、この贈与は特別受益の対象となります。
したがって、相続人が受け取った生前贈与として通常問題となるのは、「婚姻のための贈与」と「生計の資本としての贈与」になります。
しかし、「婚姻のための贈与」や「生計の資本としての贈与」が具体的にどのようなものを指すのか、法律では明確な判断基準の定めがありません。
それぞれ個別に具体的事情をもとに判断することになりますが、特別受益は遺産に組み込むわけですから、その贈与が「遺産の前渡しと言えるかどうか」が判断のポイントとなります。
したがって、その贈与が遺産の前渡しの性質でなければ、特別受益には該当しないと判断される可能性が高くなると言えます。
婚姻のための贈与も生計の資本としての贈与も、特別受益として扱われるかどうかは、その贈与が遺産の前渡しの性質をもつのかどうかを軸に、被相続人の経済状況や贈与等をした事情、他の相続人との均衡などの観点から、個別で判断されることということです 。
ここからは、「婚姻のための贈与」や「生計の資本としての贈与」の判断基準の一例を紹介します。
婚姻のための贈与
「婚姻のため」の贈与で遺産の前渡しの性質を持つものとしては、持参金や支度金などが該当すると考えられています。
一方結納や挙式費用は、特別受益というよりも慣行や社交上の出費と考えられ、特別受益には該当しないとされる場合もあります。
しかし、金額や被相続人の経済状況、贈与の趣旨等を考慮して判断されることになります。
生計の資本としての贈与
金額が多額で遺産の前渡しの性質を持つ「生計の資本としての贈与」に該当するものとしては、
- 居住用の不動産の贈与
- 住宅購入資金の贈与
- 営業資金などの事業資金の贈与
などが挙げられます。
一方、扶養義務としての援助に該当するような生活費や日常的な教育費、小遣いなど少額の生前贈与は一般的に特別受益にはならないとされています。
生計の資本としての贈与についても、金額や程度、個別の事情を考慮して判断されることになるのです。
特別受益の持ち戻し免除とは
ここまでで、特別受益分を相続財産に含めて具体的な相続分が計算されること(=特別受益の持ち戻し)を説明しましたが、特別受益が必ず持ち戻されるかというと、そうではありません。
特別受益分を相続財産には含めずに相続分を計算することもでき、これを「特別受益の持ち戻し免除」といいます。
特別受益の持ち戻し免除を行う方法
生前贈与をした被相続人の中には、事情により特定の相続人にその贈与の分だけ遺産を多く残したいと考えている場合もあります。
そのようなとき、生前した贈与を持ち戻し免除にすることで、相続分の計算にあたって特別受益を考慮する必要はなくなります。
ではこの「特別受益の持ち戻し免除」はどのようにして行うのでしょうか。
口頭での意思表示
特別受益の持ち戻し免除は、被相続人の意思表示によって行うことができます。
この意思表示の方法については、法律で明確な規定がありません。したがって、書面による意思表示だけではなく、口頭によることもできます。
しかし口頭で行っていた場合、確かにその意思表示があったのかどうか、明確に証明できるものがありません。したがって持ち戻し免除が認められては取り分が少なくなってしまう相続人がいる場合、免除の意思などなかったと、争いに発展してしまうケースも考えられます。
書面による意思表示
相続人全員が持ち戻し免除について争わなければ問題ありませんが、争いが予想される場合や、確実に持ち戻し免除を認めて欲しいときには、書面によって意思表示を明確にしておいた方がよいと言えます。
なお書面による場合その形式は問いませんが、より確実に主張できる方法としては、遺言書で残しておくことが望ましいと言えます。
黙示の意思表示
さて、前述したように書面で行うのが望ましいとした持ち戻し免除ですが、その一方で、黙示による意思表示も認められる場合があります。
【福岡高裁昭和45年7月31日決定】
被相続人が生前、法定相続分をはるかにこえる農地などの不動産の贈与した案件。
被相続人が生前から家業の農業を長男と営んでいたことや、無効となったが自筆証書遺言に全財産を長男に譲ると記載されていたことから、生前の不動産贈与について、黙示の持ち戻し免除の意思表示を認めたもの。
- 贈与の内容・金額や動機
- 被相続人と相続人間の関係
- 被相続人・相続人の職業や経済状況、健康状態
- ほかの相続人が受けた贈与の内容や金額、それについての持ち戻し免除の意思表示の有無
など、様々な事情を総合的に考慮して判断されることになります。
また、その判断については、遺産分割調停・遺産分割審判など、裁判所での争いになるケースが多いと言えます。
被相続人が持ち戻し免除のつもりで行った贈与であっても、それを明らかにしておかなければ争いの原因となり、免除が認められるかどうかは裁判所の判断によることとなってしまいます。
したがって持ち戻し免除の意思がある場合には、前述したように遺言書などの書面で明確に示しておくことが大切と言えます。
・参考文献:判例タイムズNo.260 339頁
持ち戻し免除の推定規定
持ち戻し免除については、さらに「推定規定」が存在します。
これは2019年7月1日に施行された改正法で新たに設けられた規定になります(民法第903条4項)。
この規定により、婚姻期間が20年以上の配偶者間について、居住用不動産を生前贈与・遺贈した場合は、被相続人の持ち戻し免除の意思が推定されることとなりました。
- 婚姻期間が20年以上
- 受遺者は配偶者
- 居住用の建物又は土地の遺贈又は贈与
この規定の趣旨は、長年連れ添った配偶者と同居していた土地・建物は、配偶者に贈与するのが自然であることや、残された配偶者の住居を確保する必要性にあります。
この規定が設けられたことで、遺言書などで持ち戻し免除の意思表示がない場合でも、その意思が法律上推定されるので、配偶者が遺産相続で不利益を被ることは少なくなったと言えます。
ただし、あくまでも推定規定ですので、持ち戻し免除はなかったと反証し、推定を覆すことは可能です。
さて、この推定規定では、「推定させる」という表現が使われています。似たような表現に「みなす」という用語があります。どちらも法律ではこう決める、という法律用語ですが、両者の法的効果は異なりますので、少し詳しく説明しておきましょう。
・「推定する」とは
「推定する」とは、ある事柄があった場合に、反証がない限り、その事柄について法令がこうであろうという効果を認める、という意味です。したがって反証が認められれば、その効果は認められないことになります。今回の配偶者の持ち戻し免除の規定がその例です。
・「みなす」とは
「みなす」とは、本来異なる事柄のものを、一定の法律関係につき同一のものとして認定してしまうことをいいます。したがって、「推定する」場合と異なり、反証が認められず、決まった事柄が覆ることはありません。
(例)民法第939条
相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
この場合、一度相続放棄をしてしまえば、その相続人は相続できることはありません。
特別受益の持ち戻し免除の意思は遺言で明確にしておくとよい
今回の記事では、相続人が生前贈与(特別受益)を受けた場合の相続財産への持ち戻しと、持ち戻し免除について解説しました。
特別受益については、何が特別受益に該当するのか、また該当したとして、持ち戻し免除の意思表示があったのかどうかなど、個別の事情を考慮して判断されることになり、その判断は難しいものです。
したがって、生前に特別受益にあたるような贈与を行った場合で、それについては持ち戻し免除にしたいと考えているときには、遺言書のようなかたちでその意思を明示しておくことが大切と言えます。
長岡行政書士事務所では、遺言書の作成や相続手続について、親切丁寧な対応を心がけております。
生前贈与をしていた場合の相続や遺言書の作成についてお悩みのある方は、ぜひ一度相談にいらして下さい。