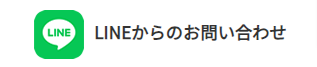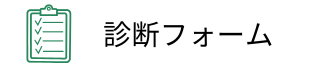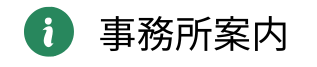「遺言書を書いたけれど、自分が亡くなったとき、遺言書通りになるのか不安がある。」
「相続人は複数いるけれど、どうやって遺言の内容を実現するのか分からない。」
「相続の手続きは色々大変そうで心配。」
遺言書には、遺言者亡き後の財産の分け方について記載しますが、いざ、実際に「その財産を分けるとき」を想像した場合、上記のような不安や悩みを持つ方も多いと思います。
遺言は故人の意思として最大限に尊重されるべきものでありますが、相続人が遺言書の内容に従ってくれるかどうかは、遺言を残すうえで大切なポイントとなります。
遺言書に書かれた内容を実現するとき、「遺言執行者」が大きな役割を果たしますが、民法改正によって権利義務に変更が生じました。
今回は、この「遺言執行者」にまつわる民法改正について解説したいと思います。
目次
遺言執行者とは
そもそも遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う権限を有する者のことをいいます。
遺言執行者をおくことは法律上の義務ではないので、遺言を書く際に必ず指定しておく必要はありません。
しかし、次のようなケースでは、スムーズな遺言の執行のためにも遺言執行者を遺言で指定しておくことが望ましいでしょう。
- 相続人がいない
- 相続人はいるものの判断能力が低下しており相続人自身で手続きを進めるのが難しい
- 複数の相続人で意見がぶつかりそう
また、遺言のなかには遺言執行者でなければ執行できないものもあります(死後認知の届出、相続人の廃除、相続人の廃除の取消しなど)。
遺言執行者でなければ執行できない手続き
遺言のなかには遺言執行者でなければ執行できないものもあります。
- 死後認知の届出
- 相続人の廃除
- 相続人の廃除の取消し
など
これらの手続きの必要性が考えられる場合は、遺言執行者を指定しなければなりません。
遺言執行者の選び方
前述のように、遺言執行者を指定することは義務ではありません。また、遺言執行者は、未成年・破産者以外であれば、誰でもなることができます。
弁護士などの専門的な資格を有しないといけないと思われそうですが、その必要はありません。遺言者の相続人でも遺言執行者にすることができるのです。
それでは、遺言執行者は誰がどう選ぶのでしょうか。遺言執行者の選び方は大きく分けて2つあります。
- 遺言書で指定する方法
- 家庭裁判所で選ぶ方法
遺言作成者が、遺言書で自ら遺言執行者をあらかじめ指定する方法
また、具体的に特定の人物を指定していなくても、「自分の死後、〇〇さんに遺言執行者を選んでほしい」というように、第三者に遺言執行者の選任をお願いする書き方もできます。
この場合は遺言者自らの意志で遺言執行者を選ぶことができます。
合わせて読みたい>>遺言執行者を指定する遺言書の書き方を行政書士が分かりやすく解説!
遺言執行者を遺言書で指定していないとき、あるいは指定していてもすでにその人が亡くなっている場合
家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。このとき家庭裁判所に選任の申立てを行うのは、相続人や受遺者、債権者などの利害関係人となります。
遺言書で指定された場合も、家庭裁判所で選任された場合も、遺言執行者に選ばれたものは、必ず引き受けなければならないという義務はありません。
引き受けるかどうかも自由です。したがって、遺言書で指定する場合は、遺言書の作成時によく検討することが大切となります。
民法改正による遺言執行者の権限と立場の明確化
遺言執行者については法律で様々なことが定められていますが、2019年に法改正があり、遺言執行者の立場や権限が明確になりました。
ここからは、法改正によって何がどう変わったのか、遺言執行者に関する法律の規定を具体的にみていきたいと思います。
まず、遺言執行者の立場と権限についてみてみましょう。
遺言執行者は遺言を執行する立場にいるわけですが、この「立場」について、民法改正前と後では以下のように定められています。
民法改正前の遺言執行者
(民法1015条)
「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす」
遺言執行者は、「相続人」(=財産を受け取る人)の「代理人」という立場であり、遺言の執行は、相続人のために代わって行うものとされていました。
しかし、遺言の内容は、必ずしもすべての相続人の希望に沿った内容であるとは限りません。
相続人に代わって行おうとしても、遺言執行者と相続人の利害が対立し、トラブルになってしまう場合もあったのです。
民法改正後の遺言執行者
(民法1012条1項)
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」
(民法1015条)
「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる」
改正では「代理人とみなす」という文言がなくなり、「遺言の内容を実現するため」という一文が明記されました。
この一文が何を意味するのかというと、遺言執行者は被相続人(=遺言者)の書いた遺言内容を実現するために職務を行うのであり、必ずしも相続人にとって利益となる行為ばかりするわけではない、ということが明確になったのです。
これにより、遺言執行者は相続人から独立した遺言を執行するための立場となり、より公正な遺言執行を行うことができるようになりました。
遺言執行者にまつわる民法改正の具体的な内容
ここからは、遺言執行者にまつわる民法改正の具体的な内容について解説します。主な要点は次の5つです。
- 遺贈における執行人の立場
- 預貯金の払い戻し・解約についての執行
- 特定財産承継遺言における権利
- 遺言執行の妨害について
- 執行者における遺言執行開始の通知義務
それぞれの詳細は次のとおりです。
遺贈における執行人の立場を明記
民法改正前、「遺贈」の履行義務について、法律では相続人と遺言執行者の権限義務が明記されていませんでした。
遺贈とは、遺言によって財産を他人に贈与することです。贈与を受けるものは、相続人に限らず誰でもなることができるとされています。
判例で「遺言執行者があるときは、遺言執行者のみが遺贈義務者となる(最判昭43年5月31日)」とされ、実務上は遺言執行者が履行していましたが、改正法でこれを明文化し、以下のように規定されました。
(民法1012条2項)
「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。」
遺言の内容が遺贈の場合、遺言執行者による履行は法律の後ろ盾が明確にできましたので、遺言執行者の権限がより強固なものにされたといえるでしょう。
預貯金の払い戻し・解約についての執行を明記
預貯金についても、払い戻しや解約権限が誰にあるのか法律に明記されていなかったことから、トラブルになる可能性もありました。
かつては、平成3年4月19日の最高裁判例をもとに、預貯金を特定の相続人に相続する遺言においては、その受益相続人に直接権利が移転するため、遺言執行者は預貯金について執行する権利義務を有しないとされました。
しかし実務上、受益相続人が金融機関で名義書換等の手続きをするには、金融機関から相続人全員の承諾が証明できる書類や印鑑証明書の提出が求められることもあり、円滑な執行が妨げられることがありました。
そこで平成24年1月25日の東京地裁判決では、預貯金に関する執行も「遺言の執行に必要な行為」であるとして、遺言執行者の職務権限とされました。
そのような実態を考慮し、改正法では以下のように明文化され、払い戻しや解約について遺言執行者の権限が法律上正式に認められました。
(民法1014条3項)
「前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預貯金又は貯金の払戻しの請求及びその預金または貯金に係る契約の解除の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。」
条文の最後、「ただし」以下に記載されているように、遺言執行者が預金の解約申し入れができるのは、その預貯金の全部が「特定財産継承遺言の目的である場合」に限られます。(※)特定財産承継遺言については後述します
また、注意したいのはここで遺言執行者に認められているのは「預貯金」の解約等の手続です。
投資信託の受益権や有価証券に関する権利など、預貯金以外の金融商品は上記条項が適用されません。
預貯金以外の金融商品が遺言に記されている際は、誰が執行者となるのか議論が残されていますが、
遺言にどのように定められているのか、遺言の解釈の問題ともなりますので、遺言執行者を指定しておくことが大切です。
この規定も遺贈の場合と同じく、法律に明記されたことによって遺言執行者の権限をより強固なものにしたといえます。
特定財産承継遺言における権利の明記
遺言執行者にまつわる法改正のひとつに、「特定財産承継遺言」が明記されたことがあります。
特定財産承継遺言とは、特定の財産を、共同相続人のうち特定の相続人に承継させる旨を記載した遺言をいいます。
たとえば「遺言者Aの土地甲を、長男Bに相続させる。」とするような遺言です。
それまでは、一般的に「相続させる旨の遺言」と言われてきましたが、法律で規定されていたものではありませんでした。
この「特定財産継承遺言」において、遺言執行者の権限も明記されました。
※特定財産承継遺言について詳しくはこちら
参考リンク:今更聞けない!特定財産承継遺言とは何か?旧法と現行法の違いも解説!
特定財産承継遺言についての規定は存在せず、「相続させる旨の遺言」と言われていましたが、この相続させる旨の遺言における遺言執行者の権利については、判例では、遺言執行者は登記手続きをする権利も義務も有していないと判断していました。(最判平成7年1月24日)
その理由は、「相続させる旨」が遺言にあった場合、その財産は被相続人の死亡時に、当該相続人に何らの行為を要せず直ちに相続により承継されると考えられたためです。
つまり、当該相続人は不動産の登記なくして権利を主張でき、所有権移転登記も単独ですることができたのです。
このため、相続させる旨の遺言では遺言執行の余地がないため遺言執行者は登記手続きをすることはできず、その義務も負わないとされていました。
このような状態でしたが、民法改正後は次のように定められたことがポイントです。
(民法1014条2項)
「遺産分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。」
(民法1014条3項)
「前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」
かつて登記がなくても第三者に権利を主張できるとされた「相続させる旨の遺言」は、特定財産継承遺言の場合、法定相続分を超える部分について、対抗要件(=登記)がなければその権利を主張することはできないとされました。
そこで、遺言執行者においても遺言内容の実現のため、被相続人が別段の意思表示をした場合を除き、単独で、相続による権利の移転登記を申請することができることになりました。
ただし、指定された相続人自身が単独で登記申請を行えることは、改正前と変わっていません。
遺言執行の妨害について
遺言執行の妨害とは、相続人が遺言の執行を妨害するような行為をすることをいいますが、法改正により、この妨害行為に対しても条文を整備しました。
(民法1013条)
「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができない。」
改正前民法では、遺言執行者がいる場合には、相続財産を勝手に処分するなどの妨害行為を禁止しているだけでした。では「違反して妨害行為をした場合にどうなるのか」については明記されておらず、解釈に委ねられていました。
そこで、改正では以下のような第2項を新たに設け、妨害行為があった場合どのようになるのかが明記されました。
(民法1013条2項)
「前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」
遺言執行者が存在する場合に、相続人が遺言の内容を妨害するような行為をした場合、その行為は無効であるとされました。
ただし、「善意の第三者に対抗することができない」とも規定されています。
これはどのようなことかと言うと、「遺言執行者がおり、本来その財産の管理処分ができるのは遺言執行者であるが、それを知らなかった人」に対しては、対抗問題になるとしているのです。
※法律上の善意と言うのは、日常用語で使う良心的と言う意味ではなく、「知らない」と言う意味合いです。
対抗問題とは、不動産の場合「登記」の問題となります。不動産の登記を先に備えた者が、その不動産を所有していることを主張できることになるのです。
従って、本来相続人Aが譲り受けるはずだった不動産を、遺言執行者がいるにもかかわらず、相続人Bが勝手に事情を知らない第三者Cに売却し、Cが登記まで済ませた場合、相続人Aは、Cに対してその不動産がAのものであると主張できなくなるのです。
これは、相続人でない者に、遺言の有無やその内容を調査する義務を負わせるのは相当でないという趣旨によるものです。
したがって、遺言の内容を知ったうえで取引したのであれば、この但し書きの対象とはならず、その妨害行為は無効となります。
執行者における遺言執行開始の通知義務
今まで説明してきた通り、法改正により遺言執行者の権限はより強いものになりましたが、それに合わせて「誰が遺言執行者なのか」を相続人が知る必要があるともいえます。
法改正時には、遺言執行者の「任務開始の通知義務」についても明記されましたので、この点についてもみてみましょう。
(民法1007条)
「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わななければならない。」
このように改正前の民法では、遺言執行者は、任務を開始してもそのことを相続人に通知する法的義務は明記されていませんでした。
(民法1007条1項)
「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。」
(民法1007条2項)
「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」
第2項を新たに設けて、遺言者は、就任後に遅滞なく遺言の内容をすべての相続人に通知することを法律で義務付けしたのです。
遺言執行者の有無は相続人に大きな影響を及ぼすため、遺言執行者に通知義務を課したものになります。
この改正により、相続人の知らないうちに遺言の手続きが進んでいた、というようなトラブルの危険性がなくなり、相続人は早い段階で遺言について知ることができるようになりました。
遺言執行者の選任は慎重に!不安な場合は行政書士へ相談を
法改正が行われたことにより、遺言執行者の権限が明確化・強化され、遺言執行者は相続人の顔色をうかがわずに、中立公正な立場で円滑に遺言執行を行えるようになったといえます。
法改正が行われたことにより、遺言執行者の権限が明確化・強化され、遺言執行者は相続人の顔色をうかがわずに、中立公正な立場で円滑に遺言執行を行えるようになったといえます。
ただしそのことはつまり、遺言執行者の立場からみると、より公正・中立な立場で手続きを行わなければならなく、強い権限を持つのに適した管理能力・手続遂行能力が求められるともいえます。
法改正後も、相続人や受遺者が遺言執行者となることは可能ですが、財産を多く受け取った相続人等はそれ以外の相続人との間に利益相反にあります。
その場合、「遺言執行者として適しているのか、公正中立に職務を執行できるのか」が問題となる可能性もあります。また、様々な手続きを管理し、処理していかなければならないことは難しく、対応しきれるのかという不安もあります。
遺言を作成する場合はそれらのことを念頭に、遺言執行者をしっかりと決めることがとても大切であり、少しでも不安がある場合は専門家に相談・依頼することも検討してみると良いでしょう。