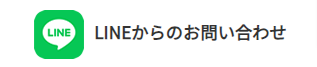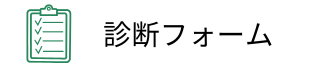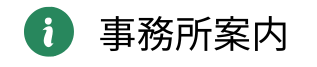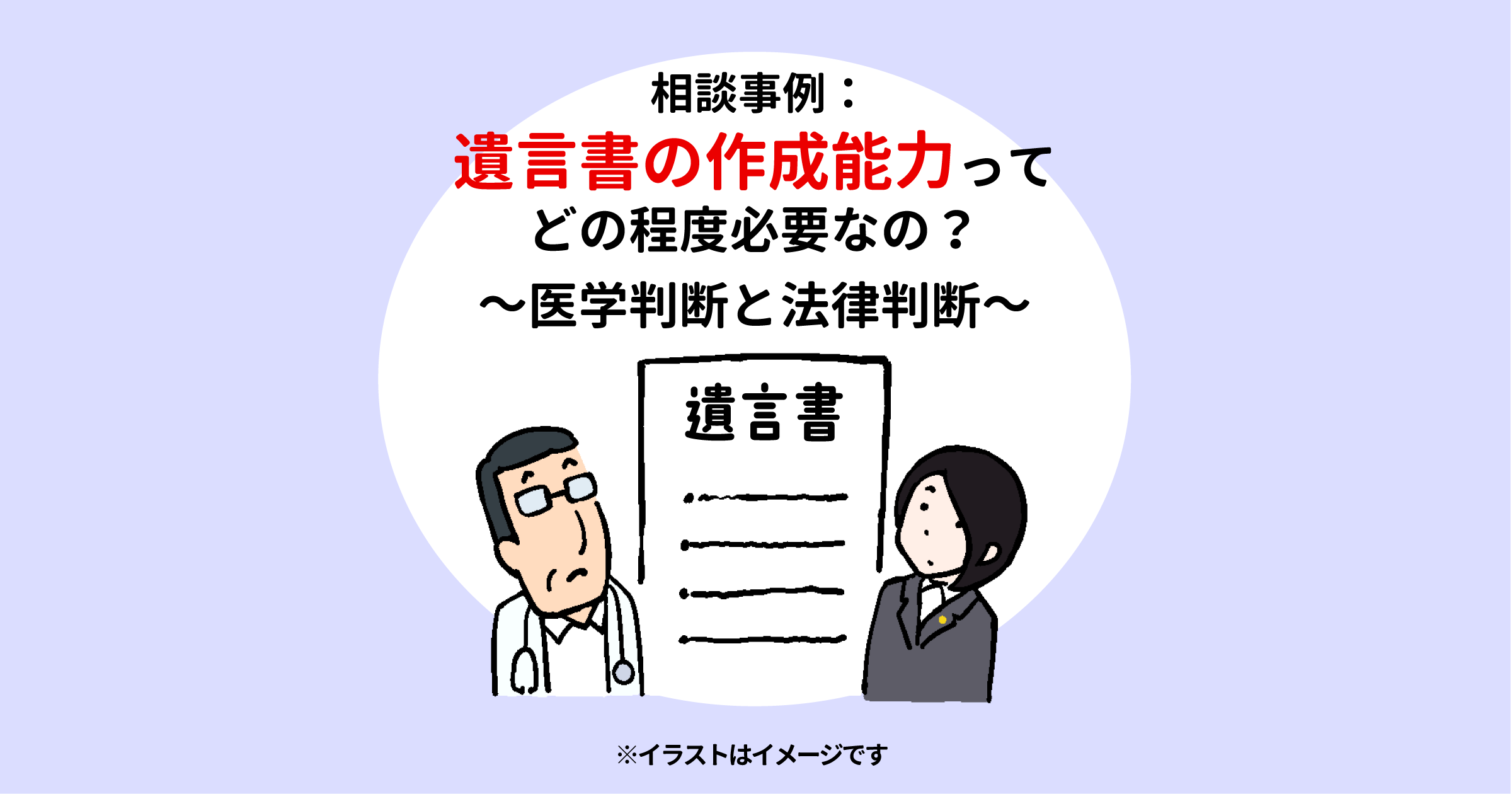
「両親に遺言を書いてもらいたいけれど、高齢でどの程度の内容が書けるのか心配。」
「遺言が残されていたけれど、作成時、判断能力があったのか疑わしい。」
「遺言は元気なうちに書いておいた方が良いのだろうか。」
遺言は、ご自身亡き後の財産の分け方について遺言者が最後の意思を伝える大事なものですが、残された家族の方にとっても、亡くなられた方が何を伝えようとしたのかを知る大切なものであります。
遺言は遺言を書かれた方の「意思の表れ」ですから、ご家族は書かれている財産の分け方について、そこから遺言者の想いを受け取り、納得して遺言に従った遺産分割をすることになります。
しかしその意思の表れである遺言が書かれた当時、本当にそれが遺言者の明確な意思によるものだったのかどうか疑わしいときには、書かれてある遺産分割の方法に納得がいかなかったり、本当にその遺言に従ってよいのか疑問を持ってしまったりする場合があります。
特に高齢化が進んだ現代社会では、遺言者が遺言の内容をどの程度理解して書いたのか、それが本当に遺言者の意思なのか、問題となる場合があります。
今回はそのような「遺言が遺言者の意思によって作成された」という点について、その判断をどうするのか、つまり遺言能力の判断基準について説明したいと思います。
目次
遺言能力の有無が問題となる事例
遺言能力の有無が問題となる事例としては、次のようなケースが挙げられます。
【事例】相談者:50代男性
遺言書が書かれたのは亡くなる少し前で、だいぶ判断能力も衰え、一人で何かするのは難しく、施設に入所した後です。
遺産は土地を含む自宅不動産と預貯金のみですが、遺言書の内容は、ほとんどすべての財産を姉に相続させるもので、私には、ごく少しの預貯金を相続させるだけの内容になっていました。父がその遺言の意味をどの程度理解して書いたのか分かりませんが、何となく納得がいきません。
父の判断能力が衰えていたことを理由に、この遺言が無効であると主張できるのでしょうか。
【回答】長岡行政書士事務所 長岡
高齢化が進んだ現代社会では、認知症を患ったり判断能力の低下がみられる高齢者の方も多く、そのような方が遺言を書いていた場合、今回のご相談者様の事例のように、書かれた遺言が有効なのかどうかが争点となる場合があります。
今回のご相談者様の事例では、遺言者の認知能力がどの程度であったのか、この時点では明確な情報がありません。また、遺言書が書かれた経緯や遺言書の内容についても具体的ではなく、この情報をもって無効の主張ができるかどうか判断することは困難です。
認知症や判断能力の低下がみられた際の遺言の作成は、遺言を作成する能力があったのかどうかという「遺言能力」の問題になります。
遺言能力が認められるかどうかについては、その判断方法が問題になりますので、今回はこの遺言能力について解説したいと思います。
このように遺言内容について納得が行かない場合、遺言能力の有無に焦点が当たるケースが多いのです。
遺言能力が認められる要件は2つ
遺言書は遺言者の意思で自由に内容を書くことができますが、有効とされるには決められた形式があり、これを守って書かなければ形式不備により無効となる場合があります。
また、この形式不備による無効のほかに、遺言者に「遺言能力がない」と判断された場合も遺言が無効となります。遺言能力とは、遺言を作成する能力のことで、遺言の内容とその結果を理解できる力をいいます。
従って、遺言が有効とされるには形式的な要件を満たしつつ、作成時に遺言者に遺言能力があることが必要となります。
この「遺言能力」について、民法では以下のように規定しています。
(民法961条)
15歳に達したものは、遺言をすることができる。
(民法963条)
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
この民法の条文から読み解けるのは、遺言をすることができるのは
- 15歳以上の者であること
- 遺言能力を有する者であること
だということです。
遺言能力を有する者(意思能力)の判断について
民法の条文では、この「遺言能力を有する者」であることの判断基準についてまで言及していませんので、遺言作成者が高齢の場合などで認知症が疑われる場合などには、特にこの「遺言能力」があったのかどうか、その判断をどのようにするのかが問題になるのです。
明文の規定はありませんので、遺言能力が争われる際には、遺言者が遺言を書くことができる状態であったのかどうか、認知症などを含めた精神状態等について医学的な判断を考慮しつつ、裁判官が遺言の内容や作成動機についても考慮した上で、遺言能力の有無を法的に判断することになります。
医学的な遺言能力の判断
医学的判断とは、遺言を作成した当時、遺言者がどのような精神状態にあったのか、遺言の内容や結果について判断できるだけの状態にあったのかを医学的な見地から判断するものです。
医学的な遺言能力の判断にあたっては、遺言者の診察にあたっていた医師による診察記録や診断書、介護を受けていた場合には介護記録や要介護認定の資料などが判断材料となります。
他に、認知症については長谷川式スケールと呼ばれる認知症の簡易検査手法があり、この点数も判断材料となります。
長谷川式スケール は、認知症の疑いや認知機能の低下を早期に発見するための簡易的な認知機能テストのことです。所要時間5~10分と短時間であり、多くの医療機関で使用されています。30点満点中20点以下で認知症の疑いありとなります。
これら資料は、医師などが客観的に遺言者を診察した結果が記されていますので、遺言能力の有無の判断にあたっては、とても大切なものとなります。
ただし、医師が認知症と判断したからと言って、それだけで遺言能力が否定されるわけではありません。
認知症と一口に言っても症状や進行具合は様々ですので、個別の案件ごとに遺言能力の有無が判断されることになります。
法的な遺言能力の判断
前述した医学的な判断は、それ単独では遺言能力があったのかどうか判断することはできません。
なぜなら、遺言の内容を理解していたのかどうかは、その遺言の内容がどの程度のものであるかにより異なるからです。内容が単純であれば理解できたとしても、複雑であれば理解が難しくなる場合があります。
したがって認知症などの精神状態を明らかにしつつ、そのような状態で理解して書いた遺言だと言えるのか、遺言内容について法的な見地から判断することも必要となります。
この遺言内容の法的判断については、遺言がどの程度複雑か、ということと、どうしてそのような内容にしたのかという遺言作成の動機や理由について合わせて判断していきます。
ここで2つの例を挙げてみましょう。
- 例①遺言内容「すべての預貯金を一人息子に相続させる」
- 例②遺言内容「不動産については長男に、有価証券についてはA社とB社を長女に、C社は次男に相続させ、預貯金は甲さんに遺贈する」
①の遺言は、子どもは息子一人で、その一人にすべての預貯金を相続させるものですから、内容は単純であり、動機も自然です。
しかし②の遺言は、複数の子どもに複数の財産を分割しており、しかも第三者の甲への遺贈もあります。
内容は①よりもかなり複雑です。また、3人の子どもに差をつけた理由が何であるのか、甲に預貯金を遺贈する理由は何であるのか、合理的に遺言者本人が説明できなければなりません。
②のような場合には、認知能力の衰えた遺言者に、第三者の甲がそそのかして書かせた可能性もあり、子ども達への相続内容も、どの程度本人の自発的な意思に基づいて決定したものか分かりませんので、遺言内容の複雑性と合わせ、作成した動機について思い違いなどがなかったかを検討していくことになります。
遺言作成の意思能力が争われた裁判例
では最後に、遺言者の遺言能力が認められた場合と、認められなかった場合の裁判例を挙げますので、実際にはどのような資料をもってどのような判断がされているのか、参考にしてみてください。
意思能力が肯定された裁判例
事件名:東京地裁平八(ワ)第1651号 遺言無効確認請求事件
【概要】
入院中の94歳の遺言者Aの嘱託に基づき作成された公正証書遺言書について、相続人の一人がそのほかの共同相続人及び遺言執行者である弁護士に対し、次の理由から遺言の無効確認を求めた事案。
- Aは遺言作成当時94歳で老人性痴呆の状態にあり、危篤状態にもあったため、遺言の内容を理解することも遺言をなし得る判断能力もなかった。
- 危篤状態のため遺言の趣旨を公証人に口授できたはずがなく、公正証書遺言としての要件を欠いていた。
【判決】
遺言者Aが遺言作成を決意するまでの経緯、病状の推移、遺言作成直前における医師の診断内容、公証人とAのやり取りなどを詳細に認定した上で、Aは遺言能力を有しており、口授の方式にも瑕疵はないと判断し、請求を棄却、遺言能力ありとして、遺言を有効としたもの。
【解説】
本件では、94歳のAに遺言の内容を理解し、遺言をなし得る判断能力があったのかどうか、また公証人との口授の際、内容を理解した上でのAの意思が発言されていたかどうかの判断が争点となりましたが、以下の点に鑑み、遺言作成時の意思能力は認められ、口授も有効と判断に至ったものです。
- 遺言者Aに老人性痴呆に基づく症状がみられたものの、日中の生活には大きな支障はみられず、CT検査による脳の萎縮等については、加齢の域をさほど超えるものではなかったこと。
- 一時危篤状態に陥ったものの、その後回復し、家族の呼びかけに対しても返答するまで回復したこと。
- 遺言作成時の状況についての医師の診断書では、意思能力が十分にあったとされたこと。
- 公証人との口授についても、Aは項目ごとに、その内容通りに各人に相続させることで良い旨を返答していたこと。
これらの様々な状況をもとに、遺言作成時において意思能力ありとし、遺言は有効であるとされました。
■参考文献:判例タイムズ967号209頁
意思能力が否定された裁判例
事件名:横浜地裁平成17(ワ)第678号 遺言無効確認請求事件
【概要】
亡母Aが作成した公正証書遺言について、相続人である子ども4人のうち2人が、他の相続人2人に対して、遺言作成当時、Aは認知症により遺言能力がなかったため、作成された遺言が無効であることの確認を求めた事案。
【判決】
Aの入通院カルテ、介護施設の記録等に基づき、公正証書遺言作成前後のAの生活状況、精神状態、担当医師らの診断内容について検討し、本件遺言当時、Aは中等度から高度に相当するアルツハイマー型の認知症に罹っており遺言能力がなかったことから原告らの請求を認め、公正証書が無効であると判断した。
【解説】
本件遺言は、公証人に嘱託し、公証人がA宅を訪問して作成されたものでしたが、以下の状況を鑑みて、Aには遺言能力があったとは認め難いという判断に至ったものです。
- 遺言作成を依頼したのは銀行員で、主導的な立場で原案を作成した可能性があった。
- 公証人が遺言を読み上げて確認した際、Aは「はい」「その通りで結構です」などの簡単な返事をしただけであった。
- 遺言の内容は、多数の不動産について複数の者に相続させ、なおかつその一部は共同して相続させるものであった。また遺言執行者の指定についても項目ごとに2名を分けて指定するなど、比較的複雑であった。
作成当時の認知症の状態から、遺言を作成した経緯や内容の複雑度において、それをなし得るだけの遺言能力はなかったと判断され、遺言が無効となりました。
■参考文献:判例タイムズ1236号301頁
認知症の人の遺言書でも無効になるとは限らない
遺言は、ご自身の思いや財産を、残される人たちに伝えるとても大切なものです。
しかし、まだ元気だから、と書くことを先延ばしにしていると、知らず知らずのうちに年月を重ね、遺言を書くことが難しい状態になってしまうことがあります。
せっかく書いた遺言でも、遺言能力がなければ無効となってしまう場合がありますし、有効なのか無効なのかを相続人で争うことになってしまう場合もあります。
この記事で紹介したとおり、遺言能力には医学的基準と法的基準があり、たとえば認知症の人の遺言書でも、必ずしも無効になるとは限りません。
そうはいっても、遺言能力の有無を争うことになると、相続人間の負担が増えてしまうことも事実です。
遺言作成を検討している方は、ぜひ元気で遺言能力に疑いのないうちに書いておくことをお勧めします。
横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言の作成に親切丁寧に対応しております。遺言作成について検討されている方、遺言能力に不安があるものの遺言書を書きたいと考えている方は、ぜひ一度、お気軽にご相談にいらしてください。ご両親の遺言作成に関する相談も歓迎しています。