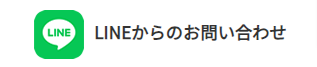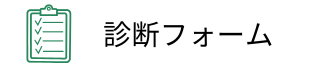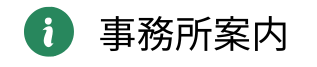「遺言を書かないと相続はどうなるのか。」
「世話になった長女に多く財産を残したい。」
「遺言で指定した財産分与の内容は、必ずその通りになるのか。」
ご自身のもしもの時に備えて、遺言の作成を検討している方もいらっしゃるかと思います。
遺言を作るということは、遺言者の財産に関して、遺された家族や身内が処分や管理に困らないようにするためであったり、感謝の気持ちを伝えたいからであったり、遺言者が実現してほしい何らかの想いが込めることでもあります。
では、遺言者が亡くなりいざ相続が開始されたとき、相続はどのようなものになるのでしょうか。
遺言が残されていれば、何も問題はなく遺言通りの相続が実現されるのでしょうか。
遺言が残されていなかった場合はどうなるのでしょうか。
遺言が残されていた場合となかった場合とで、相続人が受け取る財産の額に大きく差が生じる場合、どうなってしまうのでしょうか。
今回は、それら遺言と相続の関係について解説していきたいと思います。
目次
相続のおさらい~法定相続と遺言~
まず初めに、相続の基本である「法定相続」についておさらいしてみましょう。
相続とは、亡くなった人(=被相続人)が所有していた財産とそれに付随する一切の権利・義務を、特定の人が引き継ぐことです。
法定相続とは
人が亡くなれば、その人が所有していた財産を何とかする必要がありますから、遺言が残されていなかった場合は、法律で定められた内容の相続となります。
この法律で定められた内容の相続が法定相続となりますが、法定相続では、「相続できる人(=相続人)の範囲」と、「相続できる財産の割合」が決められています。
以後、
「相続できる人の範囲」を法定相続人
「相続できる財産の割合」を法定相続分
といいます。
法定相続人と法定相続分は、それぞれ次のように法律で定められています。
法定相続人の範囲
相続人には、優先順位があります。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
■常に相続人・・・死亡した人の配偶者
■第一順位・・・・死亡した人の子ども
その子どもがすでに亡くなっている場合は、その子どもの直系卑属(子どもや孫など)
が相続人となります(※1)。
■第二順位・・・・(第一順位の人がいないとき)死亡した人の直系尊属(父母・祖父母など)
■第三順位・・・・(第一順位の人も第二順位の人もいないとき)兄弟姉妹
その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その人の子どもが相続人となります。
(※1)このように本来の相続人が亡くなっている場合に、その子などが代わって相続する制度のことを「代襲相続」といいます。
法定相続分
法定相続分は以下の通りです。
子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる場合は、原則として均等に分けます。
■配偶者と子どもが相続人の場合
配偶者2分の1、子ども(全員で)2分の1
■配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者3分の2、直系尊属(全員で)3分の1
■配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1
以上が法定相続人と法定相続分になりますが、法定相続分については、必ずこの割合で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
相続人の間で合意があれば、法定相続分とは異なる割合で分けることができます。
遺言と法定相続分の関係
法定相続についておさらいをしましたが、では、遺言と法定相続の関係はどうなるのでしょうか。
遺言を作成するほとんどの場合が、法定相続とは異なる財産分与の内容であるといえます。
例えば、長女が老後の世話を良くしてくれた場合、他の兄弟姉妹に比べて長女に多くの財産を残したり、
折り合いが悪く音信不通の子には財産を残さないということもあります。
遺言者との関係や相続人の状況など、さまざまな理由でさまざまなパターンの遺言が作成されるのです。
そのとき問題となるのが、法定相続人間で不公平な相続分の指定が行われた場合です。
遺言がなければ法定相続により本来受け取ることのできるはずだった財産を、遺言があるために受け取ることができなかった、あるいは少ししか受け取ることができなかった相続人は、遺言の内容に従うしかないのでしょうか。
遺留分とは何か
遺言では、遺言者の財産分与について自由に内容を決定して記すことができますが、その一方で、一定の法定相続人には、「遺留分」とよばれる持ち分が法律で保障されています。
「一定の相続人」と表現したのは、遺留分がすべての法定相続人に認められているものではないからです。
遺留分の請求が認められているのは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)です。
遺留分と遺留分請求者
■遺留分を有する法定相続人
- 配偶者(常に遺留分権利者)
- 子(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(子と子の代襲相続人がいない場合に限る)
遺留分は、この一定の相続人に法律が保障している、最低限の相続分なのです。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に全財産を遺贈することもできます。
しかしそれでは、残された家族が住む家を失い、生活も困難になる可能性があります。
このように、相続人にとってあまりにも不利益な事態を防ぐため、法律で一定の相続人に遺留分という制度を定め、最低限の相続分を取得する権利を保障しているのです。
またこの遺留分は、遺留分の権利者が自ら手放すことができます。これを遺留分の放棄といいます。
この遺留分の放棄は、手続の違いはありますが、被相続人の生前・死後どちらでも可能です。
遺留分の割合
一定の法定相続人に認められている遺留分ですが、遺留分の割合は法定相続人によって異なります。
具体的な遺留分の割合は、以下の通りです。
遺留分の割合
1.配偶者と子どもが相続人の場合
配偶者4分の1、子ども(全員で)4分の1
配偶者のみ、子のみ、の場合はそれぞれ2分の1
2.配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者3分の1、直系尊属(全員で)6分の1
直系尊属のみ、の場合は直系尊属(全員で)3分の1
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者2分の1、兄弟姉妹 なし
何分のいくつ、といってもどの程度になるのかイメージがつきづらいため、次の項目で、具体的な数字で計算した例を挙げてみましょう。
遺留分の具体例
例1相続人が配偶者と子ども2人の場合
・配偶者の遺留分は4分の1
・子ども一人あたりの遺留分は、4分の1を2人で分けるので、1/4×1/2=1/8(8分の1)となります。
相続財産が6,000万円の場合の遺留分
・配偶者:6,000×1/4=1,500万円
・子ども一人あたり:6,000×1/8=750万円
例2相続人が配偶者と親(両親)の場合
・配偶者の遺留分は3分の1
・親一人あたりの遺留分6分の1を2人で分けるので1/6×1/2=1/12(12分の1)となります。
相続財産が6,000万円の場合の遺留分
・配偶者:6,000×1/3=2,000万円
・親一人あたり:6,000×1/12=500万円
遺留分の対象となる財産
遺留分の計算は相続財産をもとにされますが、この相続財産は、どこまでをいうのでしょうか。
この問いの何が問題かというと、例えば亡くなった人の財産が1,000万円だったとします。
しかし被相続人が亡くなる前に、結婚資金で200万円のお金を受け取っていた相続人がいた場合、被相続人の財産は現実に残っている1,000万円なのか、それとも先に贈与した200万円を含めた1,200万円なのか、ということであり、遺留分を計算する根拠となる財産額に違いが出てくるのです。
このように、相続人が特定の生前贈与や遺贈を受けたことを「特別受益」といいます。
相続人間の公平のために、法律ではこの特別受益分を相続開始時点の相続財産に加えて、その上で各相続人への相続分を計算することとされています
したがって、遺留分の金額もこの特別受益を加えた財産をもとにされることになります。
この特別受益については、相続開始前10年間に行われた相続人に対する贈与が遺留分侵害請求の対象となります。
なお、特別受益の対象となる贈与は「婚姻・養子縁組・生計の資本のため」になされたものに限定されます。
遺留分侵害請求とは何か
さて、今まで遺留分が何か、ということについて解説してきました。では、遺言がこの遺留分に反する内容だった場合、その遺留分を有する相続人は何ができるのでしょうか。
2019年法改正と遺留分減殺請求・遺留分侵害請求
遺言が遺留分に反する内容であるということは、つまり遺留分が侵害されているということで、このときにできる請求を「遺留分侵害請求」といい、自らの権利を回復することを内容とします。
2019年に民法の改正がありましたが、このとき、かつて「遺留分減殺請求」とよばれていた遺留分についての権利が、法改正により「遺留分侵害請求」として新たに定められました。
法改正前の遺留分減殺請求も改正後の遺留分侵害請求も、遺留分の割合など基本的な考え方に違いはありませんが、「何を請求できるか」が大きく異なります。
それぞれの請求の内容についてみてみましょう。
遺留分減殺請求権
2019年法改正前の「遺留分減殺請求」は、遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された「財産の返還」を請求する権利とされていました。
つまり、贈与や遺贈を受けた「財産そのもの」を返還するという「現物返還」が原則で、金銭での支払いは例外、という位置づけです。
また、遺留分権利者がこの遺留分減殺請求権を行使した場合、「請求権」と名はついているものの、当然に遺留分対象財産の所有権が遺留分権者に移転するとされていました。
遺留分侵害請求権
2019年法改正後に定められた「遺留分侵害請求」は、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった遺留分権利者が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分を侵害された侵害額に相当する「金銭の支払い」を請求する権利のこととされています。
減殺請求権とは異なり、遺留分侵害請求を行使しても、当然に不動産などの相続財産の持ち分を取得することはなく、その財産を所有する遺留分侵害者に対して、相当額を支払ってもらう債権を取得することになります。
遺留分侵害請求の手続き
では、遺留分を侵害されているとして「遺留分侵害請求」を行うとき、実際にはどのような手順を踏むのでしょうか。
ここで、遺留分侵害請求をするときの流れは、以下のようになります。
1~4の手順を試みて、それぞれの段階で合意に至ればそこで請求は終了となりますが、段階を追って手続きが重いものになっていきます。
なお、1~4の請求を行う前の大前提として、「遺産の金額」と「相続人は誰なのか」を確定し、自分の遺留分がいくらになるのか確定しておくことが必要です。
遺留分侵害請求の手順
- 話し合いをする。
- 内容証明郵便で請求する。
- 遺留分侵害額調停を申し立てる。
- 遺留分侵害請求訴訟を起こす。
遺留分侵害請求権の説明
1話し合いをする
まずは遺留分権利者と、遺留分侵害者の間で話し合いを行います。合意に至れば合意書を作成し、
約束通りに支払いを受けます。
2内容証明郵便で請求する
話し合いに応じてくれない場合や、話し合いでも合意に至らなかった場合、内容証明郵便で遺留分侵害請求書を送ります。
遺留分には時効(※1)があるため、上記①の話し合いに時間がかかりそうな場合や、すでに時間がたっており時効が差し迫っている場合は、あらかじめ内容証明郵便で請求書を送っておくことも必要です。
なぜ内容証明郵便を利用すべきかというと、内容証明郵便は、相手に送達された日にちも証明されるため、相手が「遺留分を請求されていない」と主張することができなくなるからです。
内容証明郵便は、「遺留分侵害請求をした事実とその日付」を確実に証明するものとなるのです。
そして請求書を送ったら、相手と話し合って遺留分の返還方法を取り決めて合意書を作成し、支払いを受けます。
3遺留分侵害額調停を申し立てる
内容証明郵便で請求をしても応じてもらえない場合や、話し合っても合意に至らない場合は、家庭裁判所で「遺留分侵害請求調停」を申し立てます。
調停では、調停委員会に仲介してもらい、相手と話し合いを行います。
合意に至った場合、「調停」が成立し、約束通りに支払ってもらいます。
4遺留分侵害額請求訴訟
調停で話し合っても合意に至らない場合は、地方裁判所で「遺留分侵害訴訟」を起こします。
訴訟で遺留分の主張と証明ができた場合、裁判所が相手に遺留分侵害額の支払い命令を出します。
これで相手が支払わなければ、差し押さえも可能です。
遺留分侵害請求権の時効
遺留分侵害請求権は、いつまでも認められているわけではありません。
遺留分侵害請求権には時効が定められており、相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年間行使しないと、時効により権利が消滅してしまいます(民法1048条)。
また、相続開始の時から10年間が経過した場合、遺留分侵害請求権は消滅してしまいます。これを除斥期間といいます。
したがって、遺留分侵害があったことを知ってから1年のうちに行使しなければ遺留分侵害請求をすることはできなくなり、たとえ侵害の事実を知らなかったとしても、相続が開始、つまり被相続人が亡くなってから10年経過した場合は請求をすることはできなくなりますので注意が必要です。
遺留分のことについては専門家にご相談ください
遺留分の制度が定められている趣旨は、著しく不公平な財産分与がなされることで、相続人の生活の安定などに支障が出ないようにすることにあります。
しかし、いざ遺留分侵害請求をするとなったとき、相続財産や相続人の把握、遺留分を算定するための財産の価額等の計算は複雑で、手続は煩雑です。
相続や遺留分に関するトラブルを未然に防ぎたい場合や遺留分が侵害されているか確認したい場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。
弊所は遺言や相続に関して親切・丁寧な対応を心がけておりますので、遺留分に関するお悩みやお困りごとがある方は、お気軽にご相談下さい。