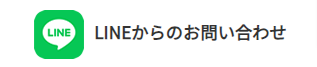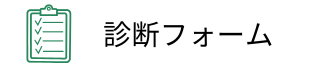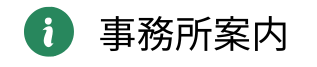突然ですが、みなさんは「遺言を書いてみましょう」と言われたとき、どのような文言を思い浮かべるでしょうか。
あるいは、すでに遺言を書こうと準備をすすめている方は、どのような書き方をしているでしょうか。
遺言は、自分自身の財産を誰に残したいのか、最終的な意思表示をするものです。この「財産を残す意思表示」をどのように書き記すのでしょうか。
例えば
「遺言者の所有する土地を、妻に相続させる。」
「遺言者の所有する株式等を、長男に相続させる。」
一般的には、上記のような書き方を思い浮かべるのではないでしょうか。
何気なく思い浮かべる、この、財産を「相続させる」という遺言の表記について、実はとても大切な意味合いがあるのです。深く考えずに表記してしまうと、意図通りに財産を承継できないかもしれません。
今回は、この「相続させる」旨の遺言、特定財産承継遺言について解説したいと思います。
目次
「相続させる旨」の遺言|特定財産承継遺言の規定
前述したように、遺言の定め方として「〇〇(財産)を△△(相続人の名)に相続させる」と記述されることがあるわけですが、このように「特定の財産を特定の相続人に相続させる」とする遺言についは、従来「相続させる旨の遺言」と呼ばれていました。
そして平成30年の民法改正で「特定財産承継遺言」という名称がつけられ、規定が明記されたのです。
特定財産承継遺言とは、特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる遺言を言い、遺産分割方法の指定を定めたものとされます。
「特定財産承継遺言」が明記されたことで何がどうなったのか、なぜその必要があったのか、法改正以前の「相続させる旨の遺言」はどのような扱いになっていたのか、旧法下と現行法の法的な性質についてみてきたいと思います。
遺言書における「相続」と「遺贈」の違い
遺言書上で誰かに遺産を渡すとしても、それは必ずしも相続人とは限りません。
ある特定の財産を、ある特定の相続人だけに承継させたい場合、「遺贈」することも考えられます(特定遺贈)。
このとき遺言書では、「〇〇(財産)を△△(相続人の名)に遺贈する」と記述します。
ここで簡単に、「相続」と「遺贈」の違いを示しておきましょう。
【相続】
被相続人(亡くなった方)の財産を、法律で定められた相続人(=法定相続人。配偶者・子ども・両親・兄弟など)が引き継ぐこと。
相続できるのは、原則、法定相続人としての権利がある人。
【遺贈】
遺言書により、無償で財産を譲ること。
遺贈を受ける人を「受遺者」という。受遺者は法定相続人でも、法定相続人以外の第三者でも、法人でもなることが可能。
「遺贈」と「相続」は、「財産を譲る」という意味ではよく似ていますが、上記のように財産を受け取ることができる対象が違いますし、ほかにも取り扱いが異なる事項はいくつかあります。
例えば不動産を引き継いだ場合、遺贈と相続では不動産の登記手続きや税金の課税負担が異なり、その点に関しては、相続の方がメリットが大きいのです。
そして平成30年の法改正で「特定財産承継遺言」として明記された「相続させる旨の遺言」ですが、かつてはその性質について、「遺産分割の指定」なのか「遺贈」なのか、解釈が分かれていました。
遺産分割の指定とは、被相続人の遺産について、共同相続人がどれだけの割合で承継するかという相続分を、遺言で定めることです。
しかし、前述の通り遺贈では登記手続きや税金の観点から負担が大きく、遺言者からは遺贈ではなく相続という形で、特定の相続人に対して特定の財産を承継させたいという希望があり、「相続させる旨の遺言」は平成14年の最高裁判例で「遺産分割の指定」に見解が統一される経緯をたどり、平成30年の法改正で「特定財産承継遺言」となり、法律で明記されたのです。
なお、厳密には「相続させる旨の遺言」イコール「特定財産承継遺言」ではありません。
特定財産承継遺言は、特定の財産を承継する遺言です。
全部の財産を承継する場合や、財産の一定の割合を承継する場合に「相続させる」旨の遺言を用いることもありますが、これらは「特定財産承継遺言」ではありません。
しかし本コラムでは、この先の解説は一旦「特定財産承継遺言」としての「相続させる旨の遺言」として記載していきます。
特定財産承継遺言と登記
ここからはより具体的に、特定財産承継遺言の実務面について紹介します。具体的には、特定財産承継遺言と登記の関係性です。
この特定財産承継遺言と登記について理解するためには、次の要素を理解しなければなりません。
- 対抗要件
- 特定財産承継遺言の効果
それぞれ順に解説します。専門的な内容になるので、もしかしたら理解が難しいかもしれません。
横浜市の長岡行政書士事務所では、特定財産承継遺言を活用した遺言作成相談にも対応していますから、実際に相談したいという方はお気軽にご相談ください。
不動産の対抗要件は「登記」
特定財産承継遺言による効果を説明する前に、まず一般的な法律用語として、「対抗要件」について知っておく必要がありますので、ここで説明したいと思います。
不動産などの物件を所有している時に、「それが自分のものである」ことを第三者に主張するには、いわゆる「対抗要件」が必要とされています。
ご自宅を所有されている方は土地や建物を購入した際のことを思い出してみて下さい。購入した際、土地や建物について「登記」をしたはずです。
不動産の場合、この「登記」が、第三者にその物件が自分のものであることを主張する対抗要件になるのです。
例をあげてみましょう。
AさんがBさんに土地を売ったとします。
その後、AさんがCさんにもその土地を売却し、Cさんがその土地を利用している場合、BさんがCさんに「その土地は私のものだから出ていけ」と主張するためには、その土地について登記をしていなければなりません。
AさんとBさんの間で交わした「土地を売る」という契約自体は有効ですが、それは第三者からは見えないことですので、誰が権利者かわからない状態にあります。
そこで民法では、「対抗要件」という制度を整備して、これを先に具備した方が勝つという仕組みをとったのです。
特定財産承継遺言の効果|遺言の効力発生時に所有権が移転
不動産の対抗要件は「登記」であることについて説明をしましたので、このことを頭の隅に置いていただいて、特定財産承継遺言の効果と登記の関係をみてきたいと思います。
ある人が亡くなり相続が発生した場合、相続人が確定的に権利を取得するためには、相続人の間で遺産分割協議を行って、故人の財産についてどう分割するか決める必要があります。
しかし特定財産承継遺言がある場合には、遺言の効力発生時に、その財産の所有権が直接指定された相続人に帰属することになります。
遺言の効力発生時とは「遺言者の死亡時」をいいますので、遺言者が亡くなると同時に、特定財産承継遺言に記載された財産が、遺言書で指定された相続人に移転することになります。
したがって、遺言で相続させる旨記載された特定の財産については、遺産分割協議の対象ではなくなります。
例えば、特定財産承継遺言によって家を長男に相続させる場合、遺言者が死亡すると同時に、長男は何もしなくても当然にその家の所有権を取得することになります。
特定財産承継遺言と対抗要件の関係
では、先ほど説明した対抗要件との関係はどうなるのでしょうか。通常は、不動産の所有権は登記をしなければ第三者にその権利を主張できないはずです。
民法177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」
この点、法改正前の「相続させる旨の遺言」では、相続人はすべての持ち分について登記なくして第三者に権利を主張できるとされていました。
しかし法改正後の特定財産承継遺言では、譲り受けた財産が法定相続分の範囲内かどうかにより、以下のように異なる取り扱いとなることが明記されました。
- 法定相続分の範囲内では登記なくして第三者に権利を主張することができる。
- 法定相続分を超える範囲については登記をしなければ第三者に対して権利の主張ができない。
特定財産承継遺言では法定相続分より多くの財産を受け取ることが多く、例えば不動産で法定相続分を超えて相続する場合、登記は必須となります。
登記をしなければ、相続人以外の第三者には受け取った不動産の権利を主張できないからです。
したがって、特定財産承継遺言で不動産を相続した場合、できるだけ早く登記することが大切といえます。
特定財産承継遺言では単独登記が可能
特定財産承継遺言は、特定遺贈と違い、遺産を渡す相手が法定相続人に限定されていることに特徴があります。
その効果として、特定財産承継遺言で不動産を相続した場合、その相続人は単独で登記申請ができます。
これに対して、特定遺贈で不動産を譲り受けた場合は、他の相続人全員と共同して登記申請をしなければなりませんので、手間がかかります。
権利を譲り受けた相続人単独で登記申請できることは特定財産承継遺言のメリットといえます。
特定の法定相続人に遺産を相続させるなら、特定遺贈より特定財産承継遺言を用いた方が、単独で手間がかからずに手続きでき、他の相続人から妨害を受けるリスクも少ないといえます。
特定財産継承遺言の注意点
最後に、特定財産承継遺言を作成する際の注意点について説明します。
注意する点は以下の2つがあると言えます。
- 遺言の解釈が分かれることがある
- 遺留分を請求される可能性がある
上記2点を説明していきます。
遺言の解釈が分かれることがある
特定財産継承遺言では、書き方によって遺言の趣旨の解釈が次のように分かれることがあります。
- 特定財産だけを譲り渡す趣旨か
- 法定相続分の中に特定財産を含める趣旨か
- 法定相続分に加えて特定財産を与える趣旨か
例えば、被相続人の財産に不動産・複数銀行の預貯金・有価証券があった場合で、それらの財産を、子ども3人が相続したとします。
そのとき遺言書に「自宅不動産を長男に相続させる」とだけ記されていた場合、遺言書の趣旨は以下1~3のどれなのか、曖昧になってしまいます。
- 長男は自宅不動産のみを相続し、その他の財産は長男以外の子どもで法定相続分に応じて分割する。
- 自宅不動産を含むすべての財産を法定相続分で分割し、長男が自宅不動産を相続する。
- 自宅不動産を除いたその他の財産を法定相続分で分割し、長男はそれに加えて自宅不動産も相続する。
したがって特定財産承継遺言では、すべての相続財産について記載した遺言とするか、遺言に記載されていない財産については分割方法を指定することが大切となります。
遺留分を請求される可能性がある
遺留分とは、法律上保障された、法定相続人が受け取れる最低限の遺産の範囲のことです。
遺留分が認められるのは、法定相続人のうち、配偶者・子や孫・父母や祖父母です。兄弟姉妹には認められていません。
※遺留分について詳しくはこちら
参考リンク①遺留分とは何か?遺留分の割合と遺留分侵害額請求権について解説
参考リンク②行政書士が解説する!遺留分を侵害する遺言とは無効となるのか?
遺言が特定財産継承遺言であっても、遺留分を侵害された他の相続人は、遺留分を侵害した金額に相当する金銭を請求する権利が認められています。
その場合、他の相続人とトラブルになる可能性もありますので、遺言者は、遺留分を十分考慮して遺言書を作成する必要があります。
もし、遺留分を考慮した遺言内容に不安がある場合は、ぜひ一度長岡行政書士事務所へご相談ください。
相続人へ確実に財産を渡すなら特定財産承継遺言を利用
特定財産継承遺言は、特定の財産を特定の相続人に譲り渡すことができますので、相続人の誰かに確実に財産を譲りたいという被相続人の意思を反映させるのに有効な方法です。
しかし一方で、遺言は思いのほかパターンや書き方が複雑で簡単ではありません。適切な書き方をしないと相続人がもめてしまったり、相続トラブルの原因となる可能性があります。
遺される人を思って作成する遺言ですから、円滑な相続になるよう、遺言作成をお考えの方は相続の経験が豊富な行政書士などの専門家に相談することをおすすめいたします。
横浜市の長岡行政書士事務所では、円滑な相談を実現できるよう、遺言作成から相続手続きまでお手伝いしています。初回相談は無料ですから、少しでも不安のある方はお気軽にご相談ください。