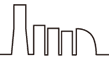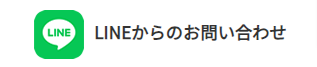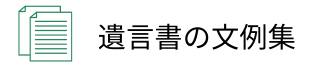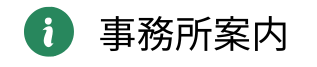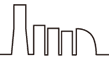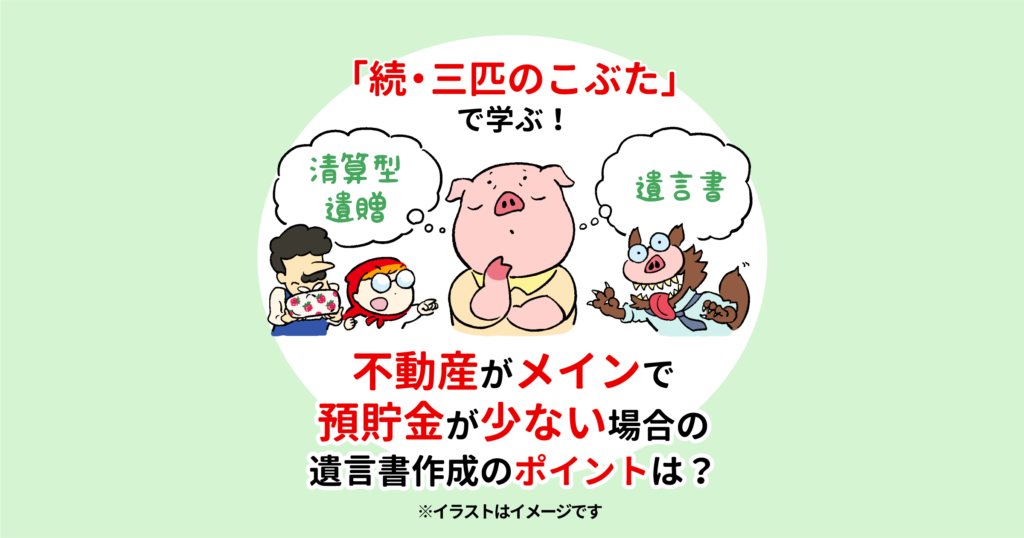
遺言書にはさまざまな財産について記載するケースが多いですが、中には不動産のみを記載したいという方もいるでしょう。
そこでこの記事では、不動産のみを記載する遺言書の書き方について、難しい法律の話になりすぎないよう、物語風に紹介します。
紹介するのはあくまでも例であるため、実際に作成するときは我々のような専門家に直接相談していただきたいですが、相談材料の一つとして参考にしてみてください。
目次
相続財産としての「不動産」の特徴
まずは相続財産として「不動産」にどのような特徴があるのか、三匹のこぶた風に見ていきましょう。
「困ったわねえ、不動産の相続、いったいどうしたらいいのかしら?」
「ひっひっひ…どうなさいましたか、母ぶたさん」
「あら? どなたかしら?」
「通りすがりのものでしてねぇ…なんでも不動産の相続がどうこうと聞こえてきたものですから…」
「まあ、よければご相談に乗って下さらない? 本当は行政書士の資格を取った赤ずきんちゃんに相談しようと思っていたんですけど」
「赤ずきんちゃんはいまお仕事で忙しいでしょうから、よければアタクシが聴きますよぅ」
「そうですか…実はいま遺言を書いていましてね」
「ひひっ…遺言ですか。それならアタクシにお任せくださいよぅ。お安い御用ですよぅ」
なんと、母ぶたはオオカミの変装に気づいていないようです。それだけオオカミが狡猾に化けているのです!
「実はうちには3人の息子がいましてね。息子たちへの相続を考えたとき、預貯金は多くはなくて、財産といったら不動産くらいなものでしてね。でもこの家を3つに分けるなんてことはできないし、どうしたらいいのかしら?」
「ひっひっひ。だったら、相続しなくて済むようにしてしまえばいいじゃないですかぁ?」
「どういうことかしら…?」
「なあに簡単な話ですよぅ…あたしが3人…いや、母ぶたさんまでみーんな食べちまえばいいんですからぁ!」
「あ、あなた! あのオオカミ…!」
「前菜はお前で決まりだぁ!」
空腹に耐えかねていたオオカミは、文字通りしっぽを出しました。よだれを垂れ流しながら、今にも母ぶたに襲い掛かろうとしたそのときでした。
「母ぶたさん! もう大丈夫よ!」
「悪いオオカミめ、またしょうこりもなくやってきたずらか!」
なんとそこへ、偶然、母ぶたに野いちごパイをお届けしようとしていた赤ずきんちゃんと、仲良しの漁師さんが飛び込んできたのです。
「いつもいつも母ぶたさんをだまそうとして! さっさと山に帰りなさい! じゃないと…」
「ひいい、わかったよぅ! 今日のところはこれくらいで勘弁してやらぁ」
オオカミは、しっぽを丸めて山の中へ逃げ帰りました。
「まったく、いつも困ったヤツずら。なまじっか変装が得意なだけに、タチが悪いずら」
「母ぶたさん、大丈夫? 間に合ってよかったわ」
腰を抜かしていた母ぶたに、赤ずきんちゃんがやさしく手を差し伸べました。
「ごめんなさいね…赤ずきんちゃん。最初から赤ずきんちゃんに相談しておけばよかったわ」
「いいのよ。詳しい話はお茶をしながらにしましょう。おいしい野いちごパイが焼けたのよ」
こうして母ぶたは、オオカミとのやりとりの一部始終を赤ずきんちゃんと漁師さんに伝えました。
赤ずきん「なるほど、3人の子ぶたさんに財産を分けるにしても、不動産をどう分けたらいいか悩ましいというわけね」
不動産の相続で意識したいポイントは次のとおりです。
- 不動産は物理的に分けられない
- 不動産は財産価値が大きく揉めやすい
不動産は物理的に分けられない
現金・預貯金などは、相続人が均等に分けることも可能です。
たとえば300万円を3人で分けるとしたら、100万円ずつに簡単に分けられます。
一方、不動産は物理的には分けられません。あっちの部屋は長男、こっちの部屋は次男、、などのようには分割できませんものね。
不動産は財産価値が大きく揉めやすい
不動産は物理的に分けることができないため、誰か一人に相続させようと思うかもしれません。
しかし不動産は財産価値が大きいため、相続できなかった他の相続人が不満を持ち、争いの原因になってしまうこともあります。
また、一つの不動産を複数人で「共有」することも可能ですが、この場合は権利関係が複雑になり、各個人が不動産を自由に処分(売却など)できないため、将来的な争いの種になることもあります。
母ぶた「不動産にはいろいろ大変なことがあるのねえ…。ところで、参考までに教えてくれないかしら? もし私が遺言書を残していなかったらどうなるの?」
赤ずきん「その場合は、兄弟ぶたさんがケンカになっちゃう可能性が出てくるわ。遺言書が作成されていないと、法定相続か遺産分割協議による分割方法になるの」
母ぶた「法定相続? 遺産分割協議?」
赤ずきん「法定相続では相続人の相続割合が決まっているのね。母ぶたさんの家を相続した場合、ざっくりいうと相続人全員の共有状態になるわけ。すると、家を賃貸にだしたり、売却したりするとき、共有している過半数以上の合意が必要になるのよ」
漁師「つまり、意見が一致しなければ、不動産を有効活用できないうえに、もめてしまうこともあるずら」
赤ずきん「しかも、共有者の1人が亡くなった場合、もっと複雑になっちゃうのよ。亡くなった共有者の相続人、つまり孫ぶたさんが共有持分を相続することになるから、不動産の名義関係とか処分手続きが複雑になっちゃうのよね」
母ぶた「まだ孫ぶたはいないけど、孫にまでそんな面倒かけたくないわね…」
漁師「遺産分割協議の場合は、協議内容に納得できない相続人がいると協議がなかなかまとまらくなってしまうずら。ここもやっかいなところずら」
赤ずきん「だから遺言書で不動産の相続の仕方を記載しておけば、法定相続によらずに遺言書通りの遺産分割ができるの」
不動産のみを遺言書に記載するなら換価処分(売却)が選択肢になる
不動産は物理的に分けられない、不動産は財産価値が大きく揉めやすいということを踏まえると、不動産のみを記載する遺言書を作る際には、換価処分(売却)を検討するのもおすすめです。
母ぶた「遺言書が大切なことは分かったけど、不動産だけしか財産がない場合、どう遺言書を書いたらいいのかわからなくてねえ…」
赤ずきん「不動産の相続が主なのであれば、大きく分けて2つのやり方があるわね。ひとつめは、不動産を特定の者に相続させる方法ね」
母ぶた「うちで言えば、兄弟のうちひとりに相続するようなことね」
赤ずきん「そうね。でも母ぶたさんの希望は、3人それぞれに均等に財産をわけたいのよね?」
母ぶた「そうね。争いごとなく、仲良くしてほしいもの」
赤ずきん「だったら、2つめの、不動産を換価処分(売却)して相続させる方法がいいんじゃないかしら」
母ぶた「換価処分というのは、一度家を売ってお金にして、そのお金を3人に分けると言うことかい?」
赤ずきん「簡単に言うとそういうことね。まず、不動産を換価処分して現金化。被相続人の債務等…母ぶたさんには借金はないようだけど、もしあれば最初に差し引いて、残った金額を3人で分けるのね」
漁師「これを清算型遺贈というずら」
赤ずきん「例えば、土地・建物の売却額が3000万円だとするでしょ。で、被相続人の債務は0円だったとする。すると、兄ぶたさん、弟ぶたさん、末っ子ぶたさんは、それぞれ1000万円づつ受け取れるってわけね」
母ぶた「わかりやすいわ。そうね、まさしくこれがいいわね」
赤ずきん「私もそう思うわ。しかも、兄弟ぶたさんはそれぞれ家を持っているから、相続財産である母ぶたさんの家が空き家にならなくて済むしね」
母ぶた「空き家じゃだめなのかい?」
漁師「固定資産税がかかってしまったり、土地建物の維持管理費の負担が出てくるから、空き家はお勧めしないずら」
母ぶた「いろいろあるのねえ…。ところで、参考までに教えてくれないかしら? もし私が清算型遺贈の遺言書を残していなかったらどうなるの?」
不動産の相続手続を進める遺言執行者を指定しておくと安心
漁師「あと、遺言を作成するときには、同時に遺言執行者を指定しておくといいずら」
母ぶた「遺言執行者?」
赤ずきん「遺言執行者は遺言を実現するために動く人のことね。例えば換価処分に反対する相続人がいたとしても、遺言書を根拠に手続きを進めるから、遺言の実現をスムーズに行えるのよ」
漁師「登記手続きとか、手続きは複雑で難しいことが多いから専門家を指定したほうがいいずら」
母ぶた「ということは、赤ずきんちゃんにお願いしたらいいわけね! なんだ、やっぱり最初から赤ずきんちゃんに話せばよかったわ。私ったら!」
赤ずきん「もちろん! 私でよければ、力になるわ。さあ、早速詳しい打ち合わせをしましょう」
こうして、母ぶたは、赤ずきんちゃんと漁師さんに遺言書の相談をし、無事に遺言書を書くことができましたとさ。
横浜市の長岡行政書士事務所は、遺言書の作成をサポートしています。また、遺言執行者として指定していただき、相続手続まで一貫してサポートすることも可能です。
初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。