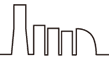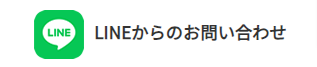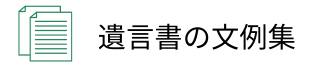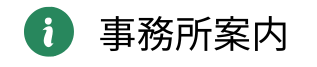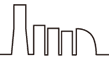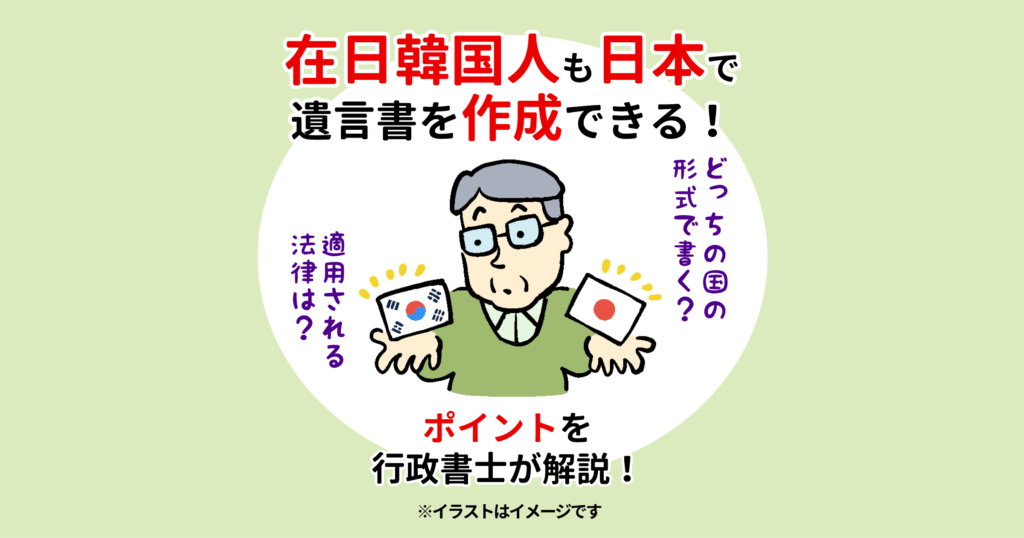
横浜市の長岡行政書士事務所では、在日韓国人の方から「遺言書を作成したい」という問い合わせを少なからずいただきます。
同じ悩みを抱いているであろう在日韓国人の方は多いと思いますので、この記事では、在日韓国人の遺言書作成について、国際私法や韓国民法の条文を具体的に示しながら、分かりやすく解説します。
なお、これは日本人・在日韓国人を問わず、遺言書を自分一人で作成すると、法的な要件を満たせていないという事態になりかねません。そのため実際に遺言書を作成する際は、ぜひ当事務所へご相談ください。(初回相談は無料です。)
目次
国際私法において、相続・遺言の根拠となるのはどの国の法律?
在日韓国人の遺言や相続で最も重要となるのは、どの国の法律が適用されるのか、という点です。
『法の適用に関する通則法』(いわゆる国際私法)第36条は、「相続は、被相続人の本国法による」と規定しています。
つまり、韓国籍を持ったまま亡くなった場合には、日本国内に財産があっても韓国民法が適用されるのが原則です。逆に、日本に帰化した場合は、相続にまつわる日本法が適用されます。
一方、遺言書については、「遺言の方式の準拠法に関する法律2条」「法の適用に関する通則法37条」が関係してきます。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律2条:遺言をした国の法律に則って作成できる
- 法の適用に関する通則法37条:遺言者の本国法による(原則)
結論としては、在日韓国人の方も、遺言をする国、つまり日本の方式で遺言書を作成できるということです。一方、遺言書の効力などについては、韓国の法律に従うことが原則となります。
しかし、工夫をすれば、日本の法律に従って相続手続を進めることも可能です。
なぜこのようなことが可能なのか、深掘りしていきましょう。
在日韓国人も日本で遺言書を作成できる
先述したとおり、在日韓国人の方であっても、遺言書は日本で作成することができます。
しかし、在日韓国人の遺言書作成では、日本の法律以外に、韓国の法律が関係してくることもあるため、押さえておきたいポイントをいくつか見ていきましょう。
在日韓国人の遺言書の方式
まず、在日韓国人の遺言の方式(作成方法)については、「遺言の方式の準拠法に関する法律2条」という法律で定められています。
ここでは、遺言者の国籍以外の国で遺言書を作成した場合、その遺言をした国の法律にに則って作成できる、と認められています。
簡単にいえば、在日韓国人の場合、日本の方式に則って遺言書を作成すればいいのです。わざわざ韓国に赴いて遺言書を作成する必要はありません。
※遺言の方式とは、日本における遺言書の種類である、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言のことをいいます。在日韓国人の方も、この3種類の遺言書のうち、好きなものを作成できます。
※長岡行政書士事務所でサポートする場合は、公正証書遺言を作成しております。
在日韓国人の遺言書の成立・効力の根拠となる法律
一方で、遺言の成立および効力に関しては、「法の適用に関する通則法37条」という法律で、”遺言者の本国法によるもの”とされています。
これは、遺言者が韓国籍であれば韓国法が適用され、日本国籍であれば日本法が適用される、ということです。
「遺言書の成立」という点については、遺言者本人に遺言能力(遺言内容を理解して、その遺言の結果がどうなるかを判断するに足りる能力)があり、なおかつ遺言が法律で定められた形式に当てはまっていれば、有効とされます。
※この要件をしっかり満たすためには、行政書士などの専門家に相談しながら遺言書を作成することが推奨されます。
また、遺言が効力を発揮するのがいつか、どういったものに影響が及ぶのか、という「遺言書の効力」については、原則としてその人の国籍、つまり在日韓国人なら「韓国」の法律が適用されます。
ややこしくなってきていますが、簡単にいうと、在日韓国人の遺言書作成で押さえるべきポイントは次の2つです。
- 遺言の方式は、日本法に則したもので作成できる
- 「成立」と「効力」については、韓国法が適用されることもある(後述しますが、遺言書を工夫することで、日本法を適用する方法もあります)
韓国民法における相続制度の特色
さて、在日韓国人が韓国籍を持ったまま亡くなった場合には、日本国内に財産があっても、韓国民法が適用されるのが原則です。しかし、そもそも韓国民法における相続制度は、どのようなものなのでしょうか?
韓国民法の相続規定(第1000条以下)によると、相続人の順位や相続分は日本法とは大きく異なります。
例えば、韓国民法第1000条は「相続人は、被相続人の直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹及び4親等内の傍系血族である」と規定しています。
日本の民法では、4親等内の傍系血族(いとこ・甥や姪・おじやおば)は相続人にはなりませんが、韓国では相続人なのです。
さらに、第1009条は法定相続分を定めており、配偶者の相続分は、直系卑属または直系尊属の相続分に比して1.5倍となる点が特徴です。
たとえば子が1人の場合、配偶者1.5:子1として、配偶者は5分の3を相続することになり、子は5分の2の相続になります。
配偶者と子の法定相続割合が1:1の日本法に比べると、韓国民法の方が配偶者の相続分が多くなることになりますね。
一方、子が2人以上に増えると、韓国の法律では配偶者は7分の3、子はそれぞれ7分の2を相続することになります。日本法(配偶者2分の1、子はそれぞれ4分の1)に比べると、配偶者の相続分が少なくなります。
このように、日本法と韓国法では、相続にまつわるルールが大きく異なるのです。
在日韓国人の財産を、日本の民法に基づいて相続する方法
なじみのない韓国の法律ではなく、日本の民法に基づいて財産を分けたい、と考えている方もいるでしょう。
実は、このような場合こそ、遺言書を活用すべきなのです。その理由は、日本と韓国の法律が、次のような関係になっているためです。
日本の通則法(国際私法)第36条では、相続について「被相続人の本国法を適用」すると明記されています。つまり、被相続人が韓国籍の場合は、たとえ日本国内の財産であっても韓国民法が原則適用されます。
しかし、韓国の国際私法第49条第1項でも「相続は被相続人の本国法による」とありますが、第2項では「被相続人が遺言に適用される方式によって、明示的に次の各号の法中いずれかを指定するときは、相続は、第1項の規定にかかわらずその法による。」と規定されています。
そして第2項第1号では「遺言により被相続人の常居所国の法律を相続準拠法と指定し、かつそこで死亡した場合」と規定されているのです。
つまり在日韓国人の場合、日本で作成した遺言書で「日本の法律を相続準拠法とする」と指定し、なおかつ日本で死亡した場合は、日本の民法に従うことになるのです。
なお、日本側の「法の適用に関する通則法41条」では、当事者の本国法によるべき場合に、その本国法に従えば日本法によるべきときは、日本法が適用されることを定めています(反致)。つまり、本国法(ここでは韓国民法)で、日本法に則った相続が認められていれば、日本法に従って相続手続を進められます。
ややこしく感じるかもしれませんが、在日韓国人の方も、日本で遺言書を作成し、日本の法律に従って相続手続を進められる、ということです。
在日韓国人が日本で遺言書を作成するときの実務上の注意点
まず第一に、日本の法律に則って相続手続を進めたい場合は、「日本国内の財産については日本法を適用する」旨の条項を盛り込むことが重要です。
また、韓国に不動産や預金がある場合、日本の遺言書だけでは処理できない可能性があることも留意しておくべきでしょう。
その他の注意点は個別的なケースによって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。横浜市の長岡行政書士事務所でも、在日韓国人の方からの相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。
在日韓国人の相続手続きの流れ
最後に、在日韓国人の相続手続きがどのような流れで進むのかも知っておきましょう。
在日韓国人の相続手続きは、日本法と韓国法が交錯するため、以下のステップで進めることが一般的です。
- 適用される法律の確認(通則法36条、韓国国際私法49条を踏まえ、日本法か韓国法かを判断)
- 相続人の確定(日本戸籍と韓国戸籍=家族関係登録簿を両方確認)
- 必要書類の収集(家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書など)
- 遺産分割の方法を決定(遺言や協議など)
- 登記・名義変更手続き(不動産、預金等)
- 税務手続き(日韓双方での相続税申告が必要となる場合あり)
なお、在日韓国人の場合、韓国の家族関係登録簿にも記録が存在します。しかし、婚姻や出生を韓国に申告していないことも多いでしょう。その場合、韓国の戸籍に家族関係が反映されず、相続人の確認が困難となります。
また、相続に必要な韓国戸籍としては、①基本証明書②家族関係証明書③婚姻関係証明書④入養関係証明書⑤親養子入養関係証明書があり、これら①~⑤が日本の戸籍に該当します。
集める書類が多いため、やはり相続手続きの専門家に依頼したほうが安心でしょう。
在日韓国人の遺言書作成は横浜市の長岡行政書士事務所に相談!
在日韓国人の方が遺言書を作成する際には、日本と韓国それぞれの法律の特性に注意したうえで、対応することが求められます。そんな時、専門知識と経験を持つ行政書士などの専門家にご相談いただければ、不安を解消し、ご希望に沿った形で安心して将来に備えることが出来ます。
「相続についてどうしたらいいのか分からない。」「遺言書を作成したいけど何を準備すればいいか分からない。」
そんな時は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。