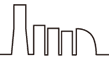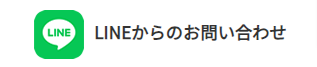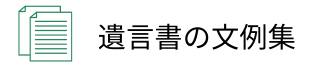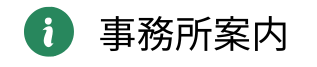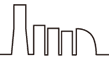アパート暮らしをしている家族の大黒柱が亡くなったら、遺族は引き続きそのアパートに住むことができるのでしょうか?
人情的に考えると「パパが死んだから追い出された」なんてことになるのはかわいそう…という意見もあると思いますが、実はこのようなケースでトラブルになることが少なくありません。
相続は一切の権利義務を承継することだということから、「賃借権」も相続の対象となるのか、アパートの賃貸借契約を遺言書に書いておいたほうがいいのか、気になるところですよね。
今回はアパートの賃借権は遺言書に書いておく必要があるのかどうかといった、賃貸住宅に暮らしている方が遺言書を作成するときのポイントについて、「推理探偵風」に解説いたします。
・・・・・
こんにちは。ぼくは名探偵として知られる明智小五郎先生の助手、小林です。
明智先生は、永遠のライバルである怪人三十面相との闘いの日々…なんてことはなく、大概が平和な毎日です。
ですので、ぼくがやっている行政書士のほうでの依頼をこなし、先生は居眠りをしたり、茶々を入れてきては暇をつぶしているというわけで。
ということで、今日も事務所に相続のご相談がやってきまして…。
ご婦人「あの…唐突ですが、夫が亡くなりまして」
明智「なんだって! コロシですか! 密室ですか! そうかそれでこの明智に犯人を捜してほしいというご依頼ですな。安心めされよ、奥方殿。で、コロシの現場はどこです? 今すぐにでも…」
ご婦人「あ、いえ…誰にも殺されてはおりませんし、亡くなったのは病院ですし、持病の悪化だったのですが…」
小林「先生、前のめりすぎますよ…」
明智「む、失敬」
目次
アパートの賃借権も相続される
借りているアパートの契約者が死亡した場合、相続の問題が発生いたします。例えば契約者が父親であったら、そこに住めないとなると、残された家族が生活に困ることになります。
ご婦人「とはいえ、困っているのは間違いないんです。実は私ども家族は、夫名義で借りていたアパートで細々と生計を立てておりましたの」
小林「ふむふむ。資料を見るに、ご主人はまだお若かったのですね」
ご婦人「ええ…。相談はここからで、夫が亡くなったら、親族から『もしかしたら今までのように、このアパートには住めなくなるかも?』などと言われて、びっくりしてしまって」
小林「なるほど、そのようなご不安をお持ちになる方は少なくないんですよ。では、詳しく解説しますね」
賃借の名義人であった夫が亡くなった後もアパートを借りる権利は相続可能です。つまり、アパートに住んでいる遺族はそのまま住むことができます。賃借権は単にアパートを使えるという権利。他の人が相続しても特に問題はありませんが、基本的には同居していた家族(相続人)が相続することになります。
小林「まず、いきなり住んでいるところを出ていけ!とはなりませんので安心してくださいね。でも、大事なことが一つ。もし新しい借主…例えば奥様が、家賃を払えないとなると、契約解除の問題が出てくるんです」
ご婦人「そうですね、そうなると大家さんも困ってしまうもの。でも、私も働いていますので、家賃は大丈夫だと思います」
小林「それなら何よりです。奥様はお若いですから大家さんとしても安心できますね」
明智「おい、小林くん! それは世間一般でいうところのセクハラではないのかね! 奥方殿がお若いから、大家さんもデレデレするだなんて、なんと破廉恥で失礼な発想だ。私は嘆かわしい! 嘆かわしいぞ、小林くん」
小林「違いますよ…そしてセクハラ発想は先生のほうじゃないですか…」
明智「ななななんだとう?」
小林「ぼくが言いたいのは、契約者のご年齢のことですよ。高齢の方の賃貸の場合、「借りている人が死ぬまで」という条件付きの内容で契約締結されていることがあるんですよ」
明智「でも、さっきご主人は若くして亡くなったと…」
小林「そうです。とはいえ、そういう条件付きの契約になっていないか、念のためチェックしたほうがいいってことなんです」
明智「…まったく君がややこしい言い方をするから…」
小林「はいはい。で、奥様、話を続けますね。肝心の賃借権の相続の流れをご説明します」
賃借権を相続するときのポイント
賃借権の相続の流れは、おおむね決まっていますが、賃料の発生時期によってその賃料をどうやって負担するのかが変わるなどの、イレギュラーな事態もあります。この章では賃借権の相続のポイントを見ていきましょう。
小林「まずは賃借権の相続のポイントはこのような感じです」
- 相続人間で遺産共有している状態になる
- 共有中は相続人全員が賃料支払い義務を負う
- 法定の相続分で賃料を負担する
- 遺産分割協議で誰が新たな賃借人かを決める
相続人間で遺産共有している状態になる
特に誰がアパートの賃借人となるか遺言などで指定がなければ、遺産を共有している状態になります。相続人の協議が確定すれば、共有状態ではなくなります。
共有中は相続人全員が賃料支払い義務を負う
遺産共有中の賃料は連帯債務とみなされます。もし賃料を請求された人が全額請求された場合、その全額を支払うことになります。
法定の相続分で賃料を負担する
賃料を支払った(立替えた)相続人は、他の相続人に対しそれぞれ法定の相続分の範囲で、立替えたぶんの賃料分の支払いを請求できます。
小林「ひとつ、ややこしいのが賃料の発生時期によって、どうやって賃料負担するのかが変わってしまうことなんですよ。つまり相続開始前に賃料が発生するパターンと、相続開始後に発生するパターンがあるんです」
ご婦人「相続発生前のパターンはどんなものなのかしら?」
小林「たとえば亡くなる前日に賃料の支払い日が来ていた。でもご主人が支払えていなかったとします。『亡くなったので払えません』になっちゃうと、大家さんとしてはたまったものではありませんね。その賃料は相続人間で法定相続割合で当然に分割されるとされています」
ご婦人「はい、普通に『家賃払ってください』となりますよね」
小林「ですので、賃料は相続人間で分割されて相続されているというふうに判断するんです。つまり大屋さんが、『相続人のみなさん、家賃、お願いしますね』と求めたら、相続人は法定相続分の中から支払うことになるわけなんです。家賃はただの金銭債務ですからね」
ご婦人「なるほど。でも家賃が発生した日が亡くなった後だったら、それは遺産にはならない…」
小林「そこなんです。遺産とは死亡時に持っていた財産ですから、相続開始後に発生した家賃は遺産ではないんです。もし賃借人が誰か具体的に定められていない間は、全相続人が賃借人になります。つまり、連帯債務を負うことで各自が全額を負担(支払い)します。だって、相続したアパートに住む権利って切り離せるものではない(Aはこの部屋、Bはこの部屋等が出来ない)ですよね。この違い、結構大きいんですよ」
遺産分割協議で誰が新たな賃借人かを決める
特に遺言で指定がなければ、話し合いでアパートの賃借人を決めます。もし誰もアパートの賃借人になりたい人がいなければアパートの解約手続きをしなければなりません。
賃借権を譲り受けた際の注意点
賃借権を相続した場合は、一般的な賃貸とは様相が違いますので、注意したほうがいいポイントがいくつか出てきます。
明智「小林くん、ひとつわからんのだが…ご主人が亡くなった奥方殿は、大家さんとの間に新しく賃貸借契約を結ぶのか?」
小林「先生にしては1000年に1度の奇跡的でまっとうな質問ですね」
明智「うっせ」
賃借権の相続は新契約ではない
小林「相続人が賃借人となってアパートに住み続けるのは、前の契約が続いているということなんです。新契約ではありませんね。つまり前の契約内容でそれを承継できる、ということです」
ご婦人「困ったわ。でも私、主人がどんな契約にしていたのか、よくわかっておりませんもの」
小林「そうですよね。アパートを相続した人が契約内容を知らなかったことで、「聞いてないよ~」という事態も出てくることがあるんです」
明智「おお、往年のダチョウ倶楽部さんか?」
小林「…違います。ですからね、奥様、賃貸人に確認するなどして、契約内容を早めに確認しましょうね。前の契約が引き継ぐことを知らないことを良いことに、不利な契約を新たに結ぶことがないようにしないとです」
ご婦人「はい」
明智「んなめんどくせーことしてられっか! なんて人もいるんじゃないのか?」
小林「そうですね、明智先生みたいなタイプですね。でも、放置していると家賃は発生し続けてしまいますから、その契約で継続するのか、契約終了にするのかは一度決め直したほうがいいんです。あと、大変失礼ではございますが…」
ご婦人「なんでしょう?」
内縁の配偶者の場合は注意が必要
小林「奥様は、内縁の配偶者ではございませんよね? あくまで念のための確認です」
明智「おい、小林くん! 失敬だぞ。失敬すぎて死刑にしたくなるほどだ。うまい! おーい、座布団一枚!」
小林「奥様、失礼なのは承知ですが、大事なことなんです。明智先生はあとでキッチリ私刑にしておきますのでご安心を…」
ご婦人「いえいえ、小林さんを信頼しておりますので。はい、内縁ではございませんが…内縁だと事情が違ってくるのかしら?」
小林「そのとおりなんです。内縁の配偶者は相続人でないため、アパートの賃借権自体を相続できないのですね」
ご婦人「んまあ、それは大変。人様それぞれご事情もおありでしょうに」
小林「とはいえ、これは被相続人(賃借人)に相続人がいるか、いないかで、判例及び法律上の扱いが異なります。例えば、相続人がいない場合は被相続人の賃借権を内縁の妻が援用したり、相続人がいる場合でも相続人の賃借権を内縁の妻が援用することで追い出されることなく、内縁の妻を保護する傾向にあるんです。まあこの辺は複雑なので別で詳しくお話ししますね!このように、相続は一筋縄でいかないので、皆様、ご不安になるんですよね」
アパートの賃借権は遺言書に書いておく必要がある?
ご婦人「ところで、私がアパートの賃借権を相続するとして、私が死んでしまったらどうなるのでしょう。先ほどから『遺言書』という言葉が何度か登場していますが、アパートの賃借権について、遺言書に書いておいたほうがいいのでしょうか」
小林「いい質問ですね。結論からすると、特段、アパートの賃借権については、遺言書に書いてなくても問題はありません。賃借権は実際に使用収益していれば当然に相続するため、実務的には書く必要はないんですよね」
ご婦人「そうでしたか。では遺言書は書かなくても心配ありませんね」
小林「いえ、アパートの賃借権以外の相続のことを考えると、遺言書を残しておいたほうが相続手続はスムーズですよ。賃貸住宅の方は、マイホームという資産はないかもしれませんが、預貯金・株式などの相続方法は、やはり遺言書でしておいたほうがいいですね」
賃貸アパートの関係する遺言書は行政書士に相談!
アパートの契約者である賃借人が死亡した場合についてお話ししてきましたが、少し複雑ですよね。特に家賃が発生する場合はその負担者も問題になることが分かりました。ただ、安心して欲しいのが、原則はいきなり追い出されることはないということです。
ご婦人「でも今回の私の杞憂は晴れましたわ。いろいろ手続きして、またご相談に寄らせていただいていいかしら?」
小林「もちろんです。そのときは明智先生がいないときにお越しくださいね」
明智「おい、邪魔者にするなよ…」
賃貸アパートの契約そのものは、必ずしも遺言書に書いておく必要はありません。
ただし遺言書はその他の目的、たとえば預貯金や株式をスムーズに相続するためにも必要なものです。
スムーズに相続手続を進めるためにも、プロのアドバイスをもらいながら作成すると安心でしょう。
横浜市の長岡行政書士事務所では遺言書の作成もサポートしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で対応しています。