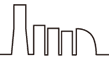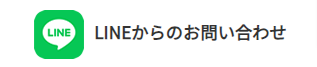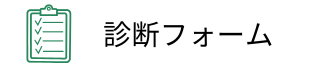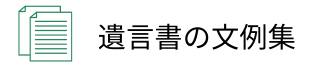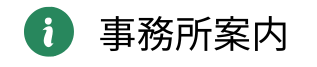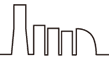「私たちのような同性のカップルは法的に守られてないような気がして不安です」
「将来自分になにかあったときにパートナーに財産の管理をお願いしたいんです。法律婚ができない同性カップルでも、そのようなことは可能ですか?」
「同性カップルの財産管理には任意後見がおすすめと聞いたんですが、任意後見とはどのような制度なのでしょうか」
横浜市の長岡行政書士事務所は相続対策のための遺言書作成をサポートすることが多いのですが、同性カップルの方からは、遺言書だけではなく、上記のような「生きている間の財産管理」について相談されるケースが多々あります。
現在の日本の法律は異性間の婚姻がその根底にあります。
例えば長い間一緒に暮らしていたパートナーでも、同性の場合は法律上の婚姻関係を結ぶことができず、少しつらい言い方になってしまいますが法律上は他人扱いとなります。
同性婚にも異性婚と同様の権利をという動きはありますが、残念ながらまだ理想とする状態に追いついてないのが現状です。
しかし、法律を理解し味方につけることである程度は異性婚に近い法律関係を「創り上げる」ことが可能です。よって、LGBT・同性カップルの方こそ法律に親しんでおく必要があると言えます。
本日はパートナーに何かがあった時に備えるための任意後見契約を説明し、その任意後見契約が持つ公正証書としての意義を解説いたします。
目次
成年後見制度とは
任意後見制度とは、成年後見制度の一形態です。そのためまずは、成年後見制度について解説します。
成年後見制度とは、認知症や障害等で判断能力が低下してしまった人に、支援してくれる人(成年後見人)をつけて社会参加を続けてもらう仕組みを指します。
※成年後見制度の本を監修いたしました>>>成年後見制度がよくわかる本
成年後見人は本人の代わりに、財産管理や契約行為をサポートすることができるので、うまく活用すれば判断力が低下しても生活に困ることは少なくなります。
より具体的には、本人の不動産や預貯金などの財産の管理や必要な福祉サービスや医療が受けられるよう介護契約の締結や医療費の支払などが含まれます。
たとえば結婚していれば、配偶者が預貯金管理などをすることもあるでしょう。しかし任意後見制度を使えば、配偶者以外の方に助けてもらうことができるのです。
そして先述したとおり、成年後見制度には2種類あります。
一つは、本人の判断能力が衰えたあとで家庭裁判所に申し立てし、後見人をつけてもらう法定後見制度です。
本人の状態の重たい順に後見、保佐、補助の3段階があり、それぞれの内容も法律によって決められています。
もう一つは、自分の判断能力が衰えたときに備えて後見人になってほしい相手と契約し、その代理権の内容や報酬等も当事者間で決定する任意後見制度です。
同性カップルには、この任意後見制度を活用することをおすすめします。
同性カップルに任意後見制度がおすすめな理由
同性カップルに任意後見制度がおすすめな理由としては、次の4点が挙げられます。
- パートナーを後見人に選任できる
- 後見人への報酬を支払う必要がない
- 同性カップルが当事者となって制度利用を進められる
- 後見人に任せる業務内容を自由に決められる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
パートナーを後見人に選任できる
法定後見制度を利用する際は家庭裁判所に申立てをしなければいけませんが、家庭裁判所が必ず自分の意図する人を後見人にしてくれるという保証はありません。
家庭裁判所は、誰が本人の権利を護るためには誰を後見人とするのが一番適切なのかを、公平・中立な立場で判断をします。その結果、弁護士、行政書士、司法書士といった第三者が選ばれる場合があります。
専門家に後見業務を担当してもらえるという安心感はありますが、例えば長年連れ添ったパートナーに後見してもらいたいという希望は通らない可能性があります。
また、外部の人にプライバシーに関与されることを好まない方もいるでしょう。
しかし任意後見制度なら、自分で誰を後見人とするか自由に選べるのです。これは同性カップルにとって、大きなメリットといえるでしょう。
後見人への報酬を支払う必要がない
後見業務を担当する報酬は本人の財産から支払うことになります。
そしてこの報酬は本人が生きている限り払い続けることになります。
士業など専門家のサービスに対する対価として後見報酬に納得ができる場合はいいのですが、例えば後見人に不満があるのに報酬を支払い続けないといけないような場合は、本人やパートナーにとっても幸せなものとは言えません。
一方、任意後見制度は、当事者の間で自由に報酬について決められます。同性カップルが法律婚夫婦のように助け合うことを目的にしているとしたら、無報酬でも構わないのです。
同性カップルが当事者となって制度利用を進められる
法定後見の申し立てができるのは4親等以内の親族等を含む一定の利害関係者に限られています。
逆の見方をすると、同性パートナーが反対しても、法律上は他人扱いなので、親族が法定後見を申し立ててしまう可能性があります。
つまり制度上、上記の一定の利害関係者に同性パートナーは当たりません。
親族の協力が得られる環境であればいいのですが、仮に同性カップルという事で親族にまだ話ができてない、もしくは理解を得られてない場合は、本人とパートナーが置き去りにされたまま後見制度の手配が進んでしまうことになります。
一方、任意後見なら、同性カップルが当事者となって制度利用を進められます。二人のタイミングで制度を活用できることも、任意後見ならではのメリットといえるでしょう。
後見人に任せる業務内容を自由に決められる
先ほど法定後見制度は本人の状態の重たい順に後見、保佐、補助の3段階があり、それぞれの内容も法律によって決まっていると述べました。
これはつまり、本人の状態に応じたテーラーメードの細かい後見業務が設定できない事を意味します。
自分の判断能力がなくなった後にどんなことをしてもらえるのかに不安がある方は、法定後見制度には向いていません。
一方で任意後見は、後見人に任せる業務内容を自由に決められます。カップル同士で話し合って、任せたいものだけを任せるということができるのです。
たとえば介護や病院の契約はパートナー、貯金管理などのお金に係わることは専門家、という風に役割を分けることも可能です。
同性カップルが任意後見契約を結ぶ流れ
もし任意後見を結んでおきたいと考えた場合は、まずは行政書士などに相談し、どのような契約書を作れば二人の願いが法律的に実現できるのか相談してみてください。
横浜市の長岡行政書士事務所でも、同性カップルのサポート経験がありますので、ご相談いただけます。(初回相談は無料です)
その後、行政書士が契約案を整えます。
公証役場に行き、任意後見契約を公正証書にしてもらいます。(公正役場とのスケジュール調整なども行政書士に依頼できます)
ここで結んだ後見契約は法務局に登記されますので、二人の契約関係が国に登録されることになります。
なお、任意後見契約はすぐに発効されるのではなく、後見が必要な状態になったら家庭裁判所に「任意後見監督人の選任」を申し立てます。
つまり、後見業務をするパートナーを監督する人を家庭裁判所に選んでもらうことになります。
パートナーといえども本人の財産を好き勝手にはできませんから、監督人への報告・チェックが必要なためです。
任意後見監督人が選任されたら、同性パートナーが任意後見人として、あらかじめ決めておいた業務に対応できるようになります。
任意後見制度はパートナーシップを後押しする
渋谷区のパートナーシップ制度が2015年に開始されましたが、そのパートナーシップ証明を申請するために必要な書類のうち一つがこの任意後見契約です。
外部参考サイト>>>渋谷区パートナーシップ証明の手引き
相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約公正証書を作成・登記していることが求められているという事は、この任意後見契約は婚姻証明書と同じように公にお互いを信頼している証となりうるという事です。
パートナーシップ制度は全国に広がりを見せていますが、パートナー証明だけでは何ら法的な効果(代理権や相続権他)は発生せず、通用する地域も当該自治体にとどまる事が多い状況です。
渋谷区のパートナーシップ制度を一つの基準として、共同生活の合意契約を結ぶことで普段の二人の関係を証明し、判断能力が落ちてしまった等のなにかあった時のために任意後見契約をお互いに結んでおけば対外的にも婚姻関係に準じた効果を持たせることができます。
実際にこの仕組みを利用して金融機関でペアローンを組んだり、二人一緒に生命保険に加入することも可能になっています。
同性カップルの任意後見契約も行政書士に相談できる!
現在の日本では同性パートナーに関し法の整備が追い付いてない部分もありますが、法を理解してうまく使えばより将来の安心が設計できます。
任意後見契約は将来判断能力が落ちてしまった時に備えるために自分で作成することができ、対外的にパートナーとの信頼関係を証明することができます。
将来について備えておきたいと考えている同性カップルの方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。任意後見契約とあわせて遺言書も作成しておくと、よりお二人の将来について安心できると思います。